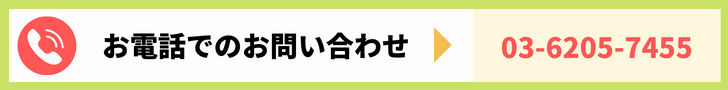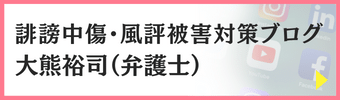以下のブログ記事は、令和6年12月25日に言い渡された知的財産高等裁判所判決(損害賠償等請求控訴事件・令和6年(ネ)第10035号・裁判所ウェブサイト)および、令和6年3月25日に言い渡された原審・東京地方裁判所判決(損害賠償等請求事件・令和5年(ワ)第70315号・裁判所ウェブサイト)を題材に、いずれも「著作権法上の職務著作」が争点となった事案について解説するものです。
はじめに
著作権の帰属をめぐる紛争の中でも、「職務著作」の成否が争点になるケースは少なくありません。職務著作(著作権法15条1項)とは、法人その他使用者が自らの発意に基づき、かつ従業者など“業務に従事する者”に「職務上作成させた」著作物で、「法人等の名義の下に公表」された場合に、原則として法人等が著作者として認められる仕組みです。
今回取り上げる二つの判決はいずれも、「ファッション色彩能力検定試験の準拠書籍」(以下「本件書籍」)に関して、執筆者(原告・控訴人)が「自分が著作者である」と主張し、対する学校法人(被告・被控訴人)は「職務著作として法人に帰属する」と反論した事案です。結果的にはどちらも、「本件書籍の著作権は学校法人に帰属する(職務著作が成立する)」 と判断されました。
本稿では、まず裁判所が認定した事実関係や法的ポイントを整理し、そこから著作権法上の職務著作に関する要件・判断基準を振り返ります。その上で、個人による創作活動と学校法人や企業に所属して行う業務との線引きがどのように裁判所で扱われているのかを解説します。
本件書籍をめぐる争点の概要
両判決に共通する大枠の争点は、以下のとおりです。
-
著作権の帰属
-
被用者個人(講師)に帰属するのか、法人に帰属するのか。
-
特に職務著作の要件(著作権法15条1項)が満たされているかどうか。
-
あるいは著作権法14条(著作名義表示による推定)が働くか。
-
-
差止請求・損害賠償請求または不当利得返還請求の成否
-
著作権を有すると主張する執筆者(講師)が、無断複製を理由に差止と金銭請求を行った。
-
しかし職務著作により学校法人が著作権を有するとされれば、執筆者(講師)の請求は棄却される。
-
-
学校法人側の故意・過失の有無
-
万一、著作権が執筆者に帰属するとすれば、学校法人による侵害の過失・故意が認定されるか。
-
判決の結論では、本件書籍が職務著作に該当するため、そもそも侵害が成立しないとして判断されていません。
-
結果として、知財高裁判決および東京地裁判決はいずれも、「本件書籍は職務著作として学校法人に著作権が帰属する」と認定し、執筆者(講師)の請求をすべて棄却しています。
職務著作の要件と両判決の認定
職務著作が成立するためには、以下の要件(著作権法15条1項)を満たすことが必要です。
-
法人その他使用者が“発意” していること
-
使用者の“業務に従事する者” が作成していること
-
“職務上作成する著作物” であること
-
“法人等の名義の下に公表” されたこと
-
“別段の定め”(契約等で異なる取決め)がないこと
両判決とも、この要件を具体的に検討しています。以下、主な争点ごとに両判決で示された判断をまとめます。
1. 「法人等の発意」について
本件書籍は「ファッション色彩能力検定試験」(以下「本件検定」)の準拠書として企画・発刊されたものでした。その検定自体を誰が企画し、その実施方法や準拠書籍の構成をどのように定めたのかが争いの背景にあります。
-
原告(執筆者) は「検定は別法人(財団法人)との共同プロジェクトであり、執筆は財団法人からの依頼で行った」と主張。
-
被告(学校法人) は「検定の企画自体は学校法人が主導し、その延長線上で準拠書籍(本件書籍)も法人として“発意”したもの」と反論。
いずれの判決も、検定の基本方針が被告理事長の指示でスタートし、学校法人の教職員が中心となって検討作業を進めたこと、また検定の受験対象として同法人が運営する専門学校生らを想定していたことなどから、「学校法人が本件書籍の制作を発意した」と認定しています。
2. 「業務に従事する者」が「職務上」作成したか
執筆者は学校法人に雇用された嘱託講師であり、週数日勤務で講義を行っていました。しかし執筆者は「講師としての勤務時間は限られ、集中して執筆などできなかった。執筆は職務ではなく個人的な活動だった」と主張しました。
これに対し裁判所は、就業規則や雇用契約で「学院の業務その他付随関連する業務」も職務範囲とされていた点、講師控室や学内で資料を借りたり打合せをしたりしていた事実、さらに執筆の対価として法人から“原稿料”が支払われていた事実などを重視し、本件書籍の執筆は「学校法人の業務に従事する者」として「職務上」行われたと判断しています。
「週何日勤務だったか」「講義時間が何コマあったか」といった勤務実態がどうであれ、「結果として学校法人内のプロジェクトの一部として従事し、学内リソースを用い、法人からの指示や報酬を得ていた以上は職務にあたる」というのが裁判所の見方です。
3. 「法人等の名義の下に公表」されているか
著作権法15条1項で要件とされるのは、「著作者として法人名義で公表されていること」です。ここで重要なのが、奥付に記載された(C)マークや“発行”・“発売元”といった表示 の分析です。
-
今回の本件書籍では、表紙や扉には財団法人名が出ていますが、奥付を見ると「発行」名義は学校法人文化学園文化出版局、(C)マークの後にも英語表記で「Bunka Publishing Bureau」とされていました。
-
執筆者は「(C)マークは著作権者を示すマークにすぎず、著作者を表示するものではない」「財団法人の名義で公表されている」と主張しました。
-
裁判所はいずれも、「Bunka Publishing Bureau」は学校法人の一組織の名称であり、社会通念上、出版局=学校法人と認識される、すなわち“法人の名義”と読むのが自然と判断。「発行」と「発売元」をはっきり区別し、「発売元」はあくまで財団法人だが、「発行」は学校法人だから著作名義は学校法人にある、と結論づけています。
「著者」として個人名や法人名が明示されているわけではなくても、奥付を含めた書籍全体の表示や形態から判断し、“法人の著作として公表されている” とみなされたわけです。
4. 別段の定めの有無
職務著作は「作成の時における契約・勤務規則・その他の定めに別段の定め」がない限り、法人が著作者として扱われます。執筆者(原告)は「本件書籍の著作権が自分に帰属する」という文言が含まれる契約や合意があったと主張していませんでした。裁判所も「別段の定めはなかった」と認定しています。
裁判所による最終判断
-
知的財産高等裁判所判決(令和6年12月25日)
控訴人の請求を棄却。「職務著作が成立し、著作者は学校法人に帰属する。よって控訴人には著作権侵害を理由とする請求権はない」と結論づけました。 -
東京地方裁判所判決(令和6年3月25日)
原告の請求を棄却。やはり「本件書籍の著作者は学校法人にあり、原告には著作権が帰属しない」として、差止請求・損害賠償請求・不当利得返還請求をいずれも退けました。
いずれの判決も、執筆者の作業実態や契約関係を精査しつつ、「学校法人が企画し、教職員である原告が職務として執筆した書籍である。公表においても学校法人の名義を表示しており、職務著作の要件がすべて満たされる」と認めています。
解説・考察
1. なぜ職務著作が厳格に認定されたのか
日本の著作権法は、まずは自然人が著作者であることを原則とします。しかし、組織が企画し、そこに従事するスタッフが職務上創作したものならば「法人を著作者」として扱う仕組みを用意し、社会的・産業的なニーズに応えています。
裁判所は、法人と被用者との“実態”を細かく見極め、「発意・指揮命令の有無」「勤務の範囲」や「名義表示」などの客観的状況を踏まえて結論づけます。本件では、
-
(ア) 執筆の契機が学校法人トップ(理事長)の指示に端を発していること
-
(イ) 執筆者が法人に雇用され、“法人関連のプロジェクト”の一環として執筆したこと
-
(ウ) 書籍の公表名義が法人出版局となっていること
-
(エ) 雇用契約に別段の定めがなく、かつ執筆者自身も出版時から長期間にわたり異議を述べなかったこと
などが大きく影響しました。
2. 個人の著作物とみなされないのはなぜか
原告は実際に書籍の大半を執筆し、図表を作成し、創作的な労力を費やしたと主張しました。しかし「創作の実質」は、著作権法上の帰属判断において決定的ではありません。職務著作は、個人がどれだけ創作に携わったかという面よりも、「事業体の発意・組織的体制の中で作成されたか」「法人名義で公表されたか」を重視します。
裁判所は、あくまでも本件書籍が「個人が勝手に書いた著作物」ではなく「法人の事業として書かれたもの」だと認定し、よって“法人が著作者”となる結論に至ったのです。
3. 実務への示唆
-
(1) 名義表示の扱い
職務著作の成否が争われる場合、書籍の奥付やクレジット表示は極めて重要です。発行者・発売元が明確に区別され、(C)マークと共にどの名称を表示するかは、後々の著作権帰属を左右しかねません。
本件のように、「表紙に他団体名」「奥付には発行として法人名(あるいは出版局名)」という構造の場合、裁判所は「実質的に法人を著作者として表示している」と判断しました。出版物の編集・制作現場では、何気ない奥付の書き方が、著作権トラブルの大きな分かれ目となる点に注意が必要です。 -
(2) 従業者による執筆と報酬形態
本件では、原告に“原稿料”が支払われていましたが、それは「講師給与」とは別枠だったことが執筆の主張の材料にもなりました。一方、裁判所は「別枠で支払われていても、法人が執筆業務を指示し、対価を支払った事実には変わりなく、むしろ法人の職務として執筆していた証拠」と捉えています。
実務では、「給与外の形で支払われる原稿料」は、執筆者にとって「自分の著作」との意識を強めることも多いですが、最終的には勤務実態や組織の指示、執筆目的などトータルで判断される点に留意すべきです。 -
(3) 別段の定めを契約で設けるかどうか
従業者が創作に大きく寄与し、しかもその創作物に高い創造性がある場合、もし社内外で「社員・講師個人の著作物にする」合意を得たいなら、雇用契約上・就業規則上でしっかり“別段の定め”を置く必要 があります。本件のようにそれがない場合は、職務著作のルールに吸収されてしまい、「個人で著作権を持っている」とは言えなくなる可能性が高いでしょう。
4. 他団体(財団法人)の関与について
本件では、学校法人とは別に関連する財団法人が検定を主催していました。執筆者は「財団法人から依頼を受けた」「財団法人の名義で出版されているはずだ」と主張しましたが、判決は「学校法人の発案・執筆・発行である」と認定しました。
外部団体(財団、関連企業、協会など)が関与する案件では、誰が企画の主体となり、どのような役割分担がなされ、どの名義で最終的に公表されたかが詳細に吟味されます。本件の両判決は、関連団体同士の覚書・契約で「学校法人が出版権を持ち、発売元は財団法人とする」と定めていた点をも根拠として、著作権が学校法人にあると結論づけました。
結論
-
知財高裁判決(令和6年(ネ)第10035号)
-
東京地裁判決(令和5年(ワ)第70315号)
いずれも、本件書籍は「学校法人の著作物」であり、執筆者個人には著作権が帰属しないとされました。
このケースは、個人の創作性が高いからといって直ちに個人が著作者となるわけではない という点を改めて示しています。法的には「法人が発意し、雇用関係のもと職務として作成し、法人名義で公表した」と認定されれば、職務著作として法人に著作権が帰属します。
著作権は、創作の現場では「誰がこんなに努力して書いたのか」という観点から争われがちですが、裁判では「著作権法の要件に合致するかどうか」がより直接的に問われます。
とりわけ法人(企業や学校法人等)に所属しながら執筆・制作に携わるケースでは、事前に“別段の定め”を取り決めていない限り、組織名義で出版されれば職務著作が成立する可能性が高い ということが分かる事例といえます。
本件判決は、教育関係や研究・制作現場だけでなく、企業内での執筆・設計・デザインなど、広く産業界での“職務著作”を巡る実務に示唆を与えるものでしょう。企業や学校法人等の事業体の内部において執筆や創作活動を行う際は、雇用契約や就業規則、出版物の奥付表記などを総合的に見直しておくことが、将来的な紛争予防の観点からも大切であると思われます。