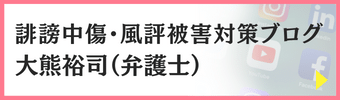生成AIと著作権のモヤモヤは、じつは「依拠」を知ると整理できる
画像生成AIでイラストを作ったり、ChatGPT で文章のたたき台を作ったり──。
こうしたことは、今では珍しくなくなりました。
ところが、その一方で、
-
「AIで作ったから著作権侵害にはならないでしょ?」
-
「有名マンガ風の絵をAIで出したけど、これって大丈夫なの?」
という不安や誤解も、同じくらい増えています。
このモヤモヤの根っこにあるのが、著作権法の世界で昔から使われている
「依拠(いきょ)」 という考え方です。
ざっくり言うと、依拠とは
「他人の作品を手がかりにして、自分の作品を作っているかどうか」ということを指します。
AIが登場したからといって、著作権の仕組みがゼロから作り直されたわけではありません。
人が創作する場合に使われてきた「依拠」の考え方を、AIにもどう応用していくか
──その調整作業が今まさに進んでいる、というイメージに近いです。
「似ている=アウト」ではない? 著作権侵害の基本の考え方
まず押さえたいのは、「似ていればすべて著作権侵害」というわけではない
という点です。
著作権侵害になるかどうかは、大きく分けると次の2段階で考えられます。
-
他人の作品を土台にしているか(=依拠があるか)
-
土台にした結果、表現がどの程度似ているか(=表現の実質的な類似)
このうち、ニュースやSNSではどうしても「こんなに似ている!」という部分だけが取り上げられがちです。
しかし、法律的には、
-
たまたま同じような発想にたどり着いただけ
-
偶然、似た構図・似た展開になっただけ
ということもあり得ます。
このような場合は、依拠がないので侵害とは言えない、という整理になります。
逆に言えば、他人の作品を出発点にしている(依拠がある)ことが前提で、
「そのうえでどこまで似ているか」が問題になる、という構造です。
人が創作する場合の「依拠」を、生活感のある例で見る
1 「アクセス」と「似ている度合い」の掛け算
裁判では、頭の中を直接のぞくことはできません。
「あなたは本当にこのマンガを読んでいなかったのですか?」と聞いても、
本人が「見ていない」と言えば、それ以上証明できないことも多いです。
そこで現実的には、
-
相手の作品がよく売れていて、目に触れる機会が多かった
-
出てきた作品が、それとかなり似ている
といった事情から、
「これは偶然というより、もともとその作品を知っていたと考えるのが自然だ」
と推測していきます。
有名なヒット曲や人気マンガほど、「アクセスがあった」と認められやすいイメージです。
2 「覚えていなかった」は逃げ道になりにくい
人の記憶はあいまいで、昔聴いたメロディや、昔読んだストーリーが、時間がたつと「どこで見たか」「誰の作品か」は忘れてしまうことがあります。
ところが、メロディの一部やストーリーの流れだけが頭に残り、新しい作品を作るときに、あたかも自分のアイデアのように出てきてしまうことがあります。
これは、作り手の側からすると「真似したつもりはない」のですが、結果としては、他人の作品の一部を再現してしまっています。
裁判例の中には、こうした現象を「無意識の依拠」として扱い、「侵害になる」と判断したものもあります。
つまり、
主観的に「パクるつもりはなかった」というだけでは足りず、客観的な事情も見られる
という点がポイントです。
3 第三者を介して伝わる「間接的な依拠」
もう少しややこしいパターンとして、
-
小説A → それを基にドラマBが作られた
-
そのドラマBを見た脚本家Cが、新しい脚本C′を書いた
というケースを考えてみます。
Cさんは小説Aを直接読んでいなくても、ドラマBを通じて、Aのストーリーや人物像に触れています。
そのうえで、C′の脚本が小説Aとよく似ていれば、「ドラマを経由して、小説にも依拠している状態」と評価されることがあります。
これが、間接的な依拠 と呼ばれるものです。
「アイデア」を使うのは自由、「表現」を真似ると危ない
著作権では、昔からアイデア(着想)と表現を区別する、という考え方が重視されています。
たとえば、
-
「田舎町で不思議な生き物と出会う少年の成長物語」
-
「タイムリープして同じ1日を繰り返す」という設定
といったレベルの話は、多くの人が思いつき得る一般的なアイデアです。
このレベルであれば、誰でも自由に使ってよいと考えられています。
一方で、
-
具体的なキャラクターの性格や口癖
-
事件が起こる順番
-
印象的なセリフやオチの付け方
が、そのまま他人の作品と重なってくると、
「アイデアではなく表現を真似ている」と評価されやすくなります。
この線引きは、
生成AIでもそのまま問題になります。
生成AIになると、何が違って何が同じなのか?
ここから、AIの話に移ります。
1 AIも「依拠+類似性」という軸は変わらない
AIが登場したからといって、
「依拠が不要になる」わけでも、「全部ダメになる」わけでもありません。
基礎にあるのは、あくまで
-
他人の作品を土台にしているか
-
表現がどの程度似ているか
という2つの問いです。
違うのは、
-
AIは膨大な数の作品をまとめて学習していること
-
具体的にどの作品をどのように学習したのか、外からわかりにくいこと
といった事情です。
ここが、人が本を1冊ずつ読んでアイデアを得る場合とは大きく異なります。
2 学習データと生成結果が「ピタッと重なる」ケース
たとえば、次のような状況を想像してみましょう。
-
特定のイラストレーターの作品だけを大量に読み込ませたAIモデル
-
ごく簡単な指示を与えただけなのに、その人の画集に載っていそうな構図・色使い・キャラクターデザインが、そのまま出てきてしまった
このような場合、
「偶然に似ただけ」と説明するのは難しくなります。
人間で言えば、
-
その画集を何度も見ている
-
そのうえでほとんど同じ絵を描いている
という状況とあまり変わりません。
こうなると、その特定の作品に依拠していると評価されやすくなります。
3 AIユーザー側の「心の中」も見られる
AIを使う人の多くは、学習データの中身までは知りません。
それでも、ユーザー自身が
-
「あの人気キャラをそのまま描いて」
-
「この小説の第1章の続きとして書いて」
などと、特定作品を意識して指示しているときは話が違います。
このようなプロンプトを残しておくと、後からトラブルになった場合に、
「もともとその作品に寄せようとしていたのでは?」と見られてしまいます。
AIだからといって、ユーザーの依拠が免罪されるわけではない、という点は重要です。
4 「作風」をマネするのと、「中身」を写すのとの違い
生成AIではよく、
-
「ジブリ風」「昭和の少女マンガ風」
-
「○○風の油絵タッチ」
など、「〜風」の指示が使われます。
ここで問題になるのは、
-
線や塗りの雰囲気、色のトーン、全体のムードといった「作風」を参考にするだけなのか
-
特定作品の構図・ポーズ・衣装・小物まで、そのまま再現してしまっているのか
という違いです。
前者は、一般的なスタイルの話なので、著作権では直接は保護されにくい部分です。
しかし後者のように、素人が見ても「これはあのキャラでしょ」と分かるレベルになると、表現そのものを真似ていると評価されやすくなります。
「AIが勝手にやった」は通用しない? 利用段階にも注意
もうひとつ見落とされがちなポイントが、生成された後の「使い方」です。
たとえば、
-
AIが出した画像が、たまたまあるマンガの一コマと似ていた
-
ユーザーがそれに気づき、「もっと近づけよう」と手作業で改変した
-
その画像をグッズや広告に用いた
こういった場合、
AIがどう学習していたかとは別に、
後から人が加えた作業の段階で依拠が問題になることがあります。
最終的に作品を公開し、ビジネスに使うのは人間です。
「AIのせいです」で責任を逃れるのは難しい、というのが現実的なところでしょう。
実務的に見て、どんなケースが危ないのか?
生成AIを使う上で、特に注意したいパターンを整理します。
1 特定の作品やキャラを名指しして、そっくり再現させる
-
「このマンガの1巻表紙と同じ構図で」
-
「某有名キャラクターがとるあのポーズを再現して」
といったプロンプトは、依拠の存在を裏付ける材料になり得ます。
商用利用を考えているなら、こうした指示は避けた方が安全です。
2 ロゴ・マスコットキャラを、ほぼそのまま使う
-
有名ブランドのロゴを少しだけ崩しただけ
-
他社のマスコットキャラと識別しにくいレベルのデザイン
このあたりは、著作権だけでなく商標権や不正競争防止法との関係でも問題になりやすい領域です。
生成AIで作ったものであっても、結果が他社のシンボルと酷似していれば、リスクは高いと言えます。
3 テキストで「どこかで見たことのある文章」がそのまま出てくる
文章生成AIを使っていると、ニュース記事や小説の一節を思わせるような表現が出てくることがあります。
一部があまりに既存作品と一致している場合、依拠と類似性が問題になることがありますので、
-
固有名詞や印象的なフレーズがそのまま出ていないか
-
段落丸ごと、どこかのサイトの文章と一致していないか
といった点をチェックすることが大切です。
生成AIを「うまく、そして安全に」使うためのヒント
最後に、クリエイターや企業が実務で気を付けたいポイントをまとめます。
1 完成したアウトプットを、冷静に見直す
-
「雰囲気が似ている程度」なのか
-
「誰が見ても、あの作品だと分かるレベル」なのか
自分の感覚だけでなく、第三者の目線を想像しながら見直すと、リスクの高いものを早めに見分けやすくなります。
2 プロンプトや制作過程のメモを残す
企業でAIを使う場合、どのような指示を出し、どのような修正を加えたのかを記録しておくと、後々、「独自に作った」という説明をするときの助けになります。
これは、人の創作でネーム・下書き・改稿履歴が重要な証拠になるのと似ています。
3 公開前に、かんたんな類似チェックをする
-
画像なら、類似画像検索サービス
-
文章なら、特徴的な文言でウェブ検索
をしてみると、明らかにそっくりな元ネタがないかを事前に確認できます。
とくに、
-
広告クリエイティブ
-
商品パッケージ
-
会社のコーポレートサイト
など、目立つところに使う素材ほど、チェックの重要度は高まります。
4 利用規約と法的リスクは別物として考える
多くのAIサービスは、利用規約の中で「商用利用OK」「一定範囲で責任を負う」などのルールを定めています。
ただし、そのサービスとの関係でのルールと、第三者との著作権トラブルの問題は、必ずしもイコールではありません。
-
規約上使えるからといって、必ずしも第三者からのクレームがゼロとは限らない
-
逆に、規約違反でなくても、利用者側が不注意だと評価される場面はあり得る
このあたりは、契約法と著作権法が別のレイヤーで動いていると理解しておくと、判断がぶれにくくなります。
おわりに:AI時代の著作権との付き合い方
生成AIが当たり前のツールになりつつある今、私たちは、「便利さ」と「権利侵害のリスク」の両方と向き合わなければなりません。
ただし、AIが出てきたからといって、著作権法がまったく別の法律に変わったわけではありません。
-
他人の作品を土台にしているか(依拠)
-
その結果として、表現がどこまで似ているか
この2つを冷静に見ていくという基本線は、人の創作でもAIの創作でも変わりません。
「AIなら全部セーフ」でも、
「AIを使ったら全部アウト」でもありません。
大事なのは、
-
どの部分が自由に使えるアイデアで、
-
どの部分が他人の「表現そのもの」に踏み込みかねないのか
を意識しながら、AIと付き合っていくことです。
生成AIは、使い方次第でクリエイターの味方にもなれば、
権利トラブルの火種にもなり得る道具です。
依拠という考え方を頭の片隅に置きながら、「便利さ」だけでなく「安全さ」も両立できる使い方を、少しずつ身につけていきたいところです。