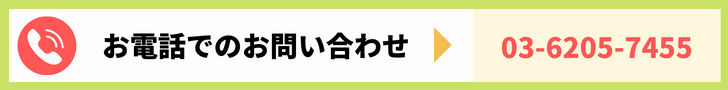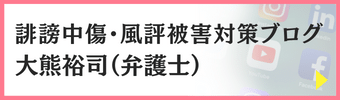Ⅰ 「紋次郎いか」が裁判となりました
皆さまは駄菓子屋のプラスチック瓶に詰められた「紋次郎いか」を覚えていらっしゃいますでしょうか。赤白ストライプのラベルと、巨大な三度笠をかぶった渡世人シルエットが目印のお菓子です。

今回取り上げるのは、そのイカ菓子と、時代小説の名キャラクター「木枯し紋次郎」をめぐる著作権・不正競争防止法訴訟です。世代を超えて親しまれてきた二つの“紋次郎”が東京地方裁判所の法廷で正面衝突したました(東京地裁令和5年12月7日判決・裁判所ウエブサイト)。
本記事では、キャラクタービジネスに携わる皆さまはもちろん、コンテンツビジネス全般に関わる方々にとっても、「キャラクターは何によって守られるのか?」という根本的テーマを考えるヒントになれば幸いです。
Ⅱ 事件の相関図
┌──原告A(作者の相続人)
│ │独占許諾
│ 原告会社(広告代理店)
│
「木枯し紋次郎」シリーズ
(小説→漫画→テレビ→映画)
│
著作権など
│ ┌─「紋次郎いか」
└──────被告(食品メーカー)
└─「げんこつ紋次郎」ほか
-
争点① キャラクターの著作物性及び著作権侵害の有無
-
争点② 「紋次郎」表示が不正競争防止法上の商品等表示に該当するか
-
争点③ 損害額1億5,126万1,000円の算定根拠の妥当性
Ⅲ 事実関係の時系列
-
1960~70年代
笹沢左保氏が時代小説「木枯し紋次郎」を連載開始しました。 -
1972年
作品が人気を博し、①主演・中村敦夫でテレビドラマ化、②C作画で漫画化、③E主演で映画化されました。 -
1974年
被告企業がイカ菓子「紋次郎いか」を発売し、1977年に図柄商標を登録しています。 -
2004~2023年(約20年間)
被告商品の年間売上はおおむね2億5,000万~2億9,000万円と推計されています。 -
2023年4月
原告らが差止・廃棄・損害賠償を求めて提訴しました。 -
2023年12月7日
東京地方裁判所が原告の請求を棄却する判決を言い渡しました。
Ⅳ 原告側の主張
-
著作権侵害の主張
-
キャラクター外観の四要素
①巨大な三度笠 ②長い道中合羽 ③長い竹の楊枝 ④長脇差
これらを組み合わせた“紋次郎キャラクター”は創作的表現であり、被告図柄は複製・翻案に該当すると主張しました。
-
-
不正競争防止法違反の主張
-
上記図柄と「紋次郎」というネーミングが原告らの商品等表示であり、周知性も高いと述べました。
-
-
損害額の算定
-
被告売上の90%が侵害商品との推計を前提に、売上×3%のライセンス料率を適用し1億3,751万1,000円を算定。さらに弁護士費用10%を加え、総額1億5,126万1,000円を請求しております。
-
Ⅴ 被告の反論
-
四要素は江戸時代の渡世人に典型的で、創作的表現ではないと主張しました。
-
「紋次郎」は自社の登録商標であり、原告の商品等表示ではないと反論しました。
-
ロイヤルティ3%の根拠が不明確で、売上計算も推測に過ぎないと指摘しました。
Ⅵ 裁判所の判断
1 キャラクターの著作物性について
一話完結形式の連載作品に登場するキャラクターは抽象概念にとどまり、著作権法2条1項1号の「著作物」ではない(最判平成9年7月17日・ポパイ判決を援用)。
裁判所はポパイ判決の理屈を、小説・テレビ・映画にわたる連載小説のキャラクターにも適用しました。つまり著作権侵害を主張するには「どの作品の・どの部分がコピーされたか」を具体的に特定しなければならないとしたのです。
さらに四要素については、渡世人の定番的なアイテムであり創作的表現とは言えないとして、著作物性を否定いたしました。
2 被告図柄との同一性について
被告図柄は笠を背丈ほどに誇張し、顔の数倍もある棒状物をくわえたコミカルな描写です。裁判所は「原告が同一性を主張できる部分自体が創作的表現に当たらない上、外観も大きく異なる」として複製・翻案性を否定いたしました。
3 商品等表示性について
不正競争防止法の「商品等表示」は、商品や営業主体を示す二次的意味(セカンダリー・ミーニング)が必要です。しかし「紋次郎」はキャラクター名にとどまり、原告らのライセンス事業を想起させる周知性も証明されませんでした。したがって混同のおそれはないと判断されました。
4 結論
-
請求棄却(差止・廃棄・損害賠償いずれも認めず)
-
訴訟費用は原告負担
原告にとっては完敗という厳しい結果となりました。
Ⅶ 判決別紙をビジュアルで確認します
●被告商品目録(判決別紙)・・・赤白ストライプに渡世人シルエットのラベルが並びます。【写真2‐5】



●被告図柄目録・・・巨大な笠を掲げ疾走する白黒シルエットです。

●本件紋次郎表示目録・・・テレビ版のワンシーンで、まさに“長合羽+長楊枝”の姿が写っております。

こうして画像を並べて見ますと、被告図柄がかなりデフォルメされていることが一目でお分かりいただけるかと思います。裁判所が同一性を否定した理由も納得できるのではないでしょうか。
Ⅷ 実務上の5つの示唆
-
キャラクター自体は著作権だけでは守りにくいです
まずは作品中の具体的な絵・文章・台詞を証拠化する必要があります。 -
商標登録は早い者勝ちです
キャラクター名やロゴマークは、出所表示になる前に先取りされるリスクがあります。 -
ライセンス契約で派生造形の帰属を明確にしましょう
テレビや映画化で追加されるデザイン要素の帰属を契約条項に盛り込むことが重要です。 -
不正競争防止法は万能ではございません
周知・著名性や混同惹起の立証が不十分ですと救済手段にはなりづらいです。 -
訴訟戦略は“具体的特定”が鍵です
侵害態様や争点を詳細に固めてから提起しないと、門前払いを受ける可能性があります。
Ⅸ まとめ-“紋次郎”が残した宿題です
本判決は、キャラクター保護の難しさを改めて浮き彫りにしました。著作権法で守られるのは具体的な「表現」に限られます。キャラクターの独自性や経済価値をカバーするには、商標・意匠・不正競争防止法などを組み合わせた多層防御と、契約・ブランド管理の運用体制が欠かせません。
もし原告側がテレビ版の映像カットや漫画の1コマと被告図柄との対比表を提示していたら、あるいは商標を先取りしていたら、訴訟の行方は変わっていたかもしれません。
訴訟が終わってから「もしも」を語っても遅いものです。キャラクタービジネスを展開する際は、開発段階から法務部門とマーケティング部門が連携し、権利設計と証拠化を同時進行で進めていただきたいと思います。
これからも令和の法廷では“推しキャラ”をめぐる新たな紛争が生じるでしょう。次はどの作品が、どのような理屈で争われるのかー判例ウォッチはまだまだ続きます。