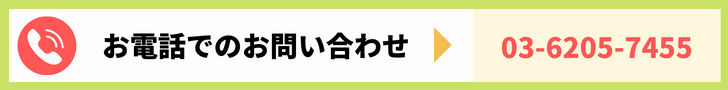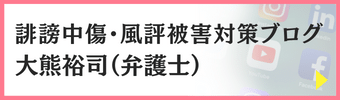【はじめに】
本稿では、知的財産高等裁判所令和3年5月17日判決(不当利得返還等請求控訴事件・同附帯控訴事件、令和2年(ネ)第10065号、令和3年(ネ)第10009号・裁判所ウェブサイト)および、これに先立つ東京地裁令和2年11月16日判決(不当利得返還等請求事件、平成30年(ワ)第36168号・裁判所ウェブサイト)を題材に、いわゆる「サウジアラビア電子機器・家電製品研修所向け教務管理システム」(以下「本件システム」)をめぐる著作権侵害・著作者人格権侵害の成否が争われた事案について解説します。両判決は、大学・専門学校等が海外教育支援事業の一環として開発を委託したシステムの帰属や、委託者側がシステム開発者のプログラムを独断で利用・改変した場合の責任について、幾つもの論点を提示する興味深い事例です。著作権法上の「職務著作」や複製権・公衆送信権(送信可能化権)・翻案権・同一性保持権など、IT技術分野の開発委託で生じやすい問題が多角的に論じられています。
以下では、まず第一審(東京地裁判決)で示された事実関係・争点・判断を整理し、その上で知的財産高裁(知財高裁)による控訴審・附帯控訴審の判断の概要を紹介し、最終的な帰結について解説を試みます。
1 事案の概要
(1)当事者関係
-
控訴人・原告
大学卒業後、システムエンジニアとして主に教育・学習支援システムの開発に従事し、その後ある専門学校(被控訴人学園が設置)に非常勤講師(教育嘱託職員)として勤務する人物。今回問題となるプログラム「本件プログラム」を自ら作成したと主張する。 -
被控訴人学園(被告学園)
専門学校や大学を運営する学校法人。サウジアラビアの電子機器・家電製品研修所(SEHAI)における教務管理システム開発を受託し、その一部作業を原告に委託した。 -
被控訴人センター(被告センター)
中東・北アフリカ諸国との産業・通商協力を行う一般財団法人。本件では経済産業省資源エネルギー庁の補助事業(サウジアラビアへの教育支援)を実施し、被告学園に業務を委託した。
(2)開発経緯の概略
被控訴人センターが経産省から補助事業の採択を受け、サウジアラビアの研修所であるSEHAIの自立運営への協力事業を推進。
-
被控訴人学園(専門学校サイド)は、被控訴人センターから一部業務を受託。
-
原告は非常勤講師契約とは別個に、本件システム開発を約束され、自宅で作業しつつプログラムを作成。本件プログラムは、学生の出欠や成績管理、時間割等を一元管理するWebシステムのプログラム群である。
(3)争点化した著作権・著作者人格権侵害の態様
-
著作権の帰属
被告学園側は「職務著作である」とか「著作権の譲渡契約があった」と主張。これに対し原告は「職務著作には当たらず、譲渡契約も成立していない」と争った。 -
被告学園の具体的行為
-
原告が参考用に送付したプログラム複製物(被告学園プログラム)を、被告学園サーバーにアップロードして実質的に公衆(少なくとも複数関係者)に送信可能化した。
-
さらにシステムを改変して機能拡張を行い、研修先のSEHAIでデモを実施(翻案、同一性保持権侵害の可能性)。
-
原告に無断で氏名表示をせずプログラムを使い続け(氏名表示権の問題)。
-
兼松エレクトロニクス社にプログラムを開示し、再委託して開発を継続させようとした点(複製権・貸与権の問題)など。
-
(4)原告の主張と金銭請求
-
原告は「開発委託費用相当」「プログラムの利用料相当額」「著作者人格権侵害に対する慰謝料等」を不当利得として合計500万円超の支払いを求めた。
-
法的構成は著作権侵害・著作者人格権侵害によって被告らが得た利益の返還を求めるという「不当利得返還請求」だった。
2 第一審(東京地裁)判決の概要
(1)著作物性・著作権の帰属
裁判所は、プログラムは当然「著作物」に当たることを認めたうえで、職務著作か否かを慎重に検討しました。結論は以下のとおりです。
-
職務著作は否定
-
原告は非常勤講師としての業務とは別に、追加報酬を得てプログラムを自宅で開発していた。作業場所や時間も原告が管理し、被告学園からの具体的指揮命令はなかった。
-
よって著作権法15条2項の職務著作には該当しない。
-
-
譲渡の事実も否定
-
被告学園が支払った105万円は労務対価とみられ、著作権の対価とは言えない。
-
途中で譲渡契約案が作成されかけたが、最終的に両者の合意には達しなかった。
-
結局、本件プログラムの著作権者は原告個人に帰属すると認定。
-
(2)具体的な侵害行為の認定
地裁は、被告学園の行為のうち、著作権侵害と認めたもの・認めなかったものを整理しました。
-
被告学園サーバーへのアップロード
-
公衆送信権(送信可能化権)および複製権の侵害と認定。
-
送信対象は限られた関係者にID/PWを配布しただけでも「公衆」の範囲に該当するとした。
-
-
被告学園プログラムの改変
-
新たに機能を追加するなど、原告のプログラムの表現上の本質的特徴を維持して改変したと判断。よって翻案権・同一性保持権の侵害が成立。
-
-
氏名表示権・公表権侵害の成否
-
一部、研修でのデモにおける公表やウェブサイトにおける未表示が問題となったが、大々的に公衆に公開したとまでは言えない部分もあり、争点ごとに認容・棄却が分かれた。
-
もっとも、一定期間ウェブサイト上に実質的アクセス可能な状態になった点については氏名表示権、公表権の侵害が認められた。
-
-
兼松エレクトロニクス社への開示
-
電磁的に複製した点は複製権侵害だが、翻案権侵害については具体的改変の事実が認められないとして、原告の請求は一部棄却。
-
-
被告センターの関与
-
被告学園とは別法人であり、具体的に著作権侵害行為を指示・共同しない限り侵害責任を負わないと判断。原告がセンターに対しても連帯責任を追及したが、裁判所は「関与が認められない」として請求を退けた。
-
(3)不当利得の額の算定
-
裁判所は、著作権侵害行為による利用料相当額として「20万円」が相当と判断。
-
原告が主張した「開発委託費用相当」「精神的苦痛に対する慰謝料」「調査費用」「弁護士費用」などは、不当利得として被告学園に帰属したものではないとし、認容しなかった。
-
遅延損害金の起算日は、原告が不当利得返還請求の意思を明確に示した平成25年9月11日の翌日とされた。
(4)結論(東京地裁)
-
被告学園に対して、不当利得返還請求権に基づき20万円および平成25年9月12日から完済まで年5%の金員を支払うよう命じ、その他の請求(総額500万円請求)はすべて棄却。
-
被告センターに対する請求はすべて棄却。
3 控訴審(知的財産高裁)判決の概要
(1)控訴の趣旨
-
原告(控訴人)
第一審判決で認容額が20万円に留まった点に不服し、著作権侵害による損害をより高額(160万円)と認めるべきなどとして控訴。 -
被告学園(附帯控訴人)
第一審で認容された20万円も支払い義務がないと主張し、原告の請求を全面的に棄却すべきとして附帯控訴。
(2)知財高裁の判断
結論的には、控訴審でも地裁の判断が維持される形となり、被告学園に対する請求は「20万円+遅延損害金」の範囲でのみ認容され、それ以外は棄却となりました。被告センターに対する主張も同様に棄却です。
具体的な争点としては、主に以下が検討されました。
-
共同行為(被告センターの責任)
-
原告は、被告センターが「共有著作権」を主張していた以上、学園の侵害行為を黙認したのだから責任を負うべきと再度主張。しかし、知財高裁は「具体的に共同行為や黙示の同意を認める証拠がない」と判断し、棄却。
-
-
損害額算定
-
原告は著作権法114条1項(譲渡数量×利益)または3項(ライセンス料相当)に基づき損害額を大きく評価すべきと主張したが、高裁も「客観的な根拠に乏しく、20万円を超える損害の立証は不十分」として原審と同じ結論へ。
-
-
附帯控訴(被告学園)
-
被告学園の「20万円すら支払う必要がない」とする主張も排斥。原審判決を追認。
-
最終的に「本件控訴及び附帯控訴はいずれも棄却」され、第一審判決(20万円+遅延損害金のみ認容)が維持されました。
4 検討・解説
本件は、海外教育支援という公共性のある補助事業の下で進められたシステム開発プロジェクトにおいて、途中で開発者(原告)と学園側が対立し、最終的に著作権侵害が認定されるに至った事例です。学園側としては、最初から契約を明確に取り交わすべきところを曖昧に進めたことで、開発者側の著作権が十分に保護される結果になりました。一方、原告としては、請求額の大半が認められず、実際の認容額は20万円にとどまるという点が特徴的です。
以下に主要論点ごとのポイントをまとめます。
-
職務著作の要件
-
著作権法15条2項の職務著作が成立するためには、雇用関係またはこれに類する指揮監督下で、かつ職務上作成された著作物であることが必要です。本件のように「非常勤講師の職務」と「システム開発」が別契約に近い形で進められ、場所や時間などを原告が独自に管理していたケースでは職務著作は認められないとされました。
-
大学や専門学校で非常勤講師とコラボしてシステムを作る際は、安易に職務著作と思い込まず、雇用か業務委託か、対価の性格等を明確に整理する必要があるでしょう。
-
-
譲渡契約の不成立
-
著作権は財産権として譲渡し得るものの、その旨の契約(書面化が望ましい)がなければ譲渡は成立しません。本件では契約書案まで作成されたものの締結されず、さらに学園が支払った105万円も「開発費用」扱いと認定。よって著作権の譲渡は認められませんでした。
-
結果として、学園側は「勝手に(あるいは誤解の下)プログラムを利用・改変していた」とされ侵害が認定されました。
-
-
複製権・公衆送信権・翻案権・同一性保持権の侵害
-
学園サーバーへのアップロード、ログイン制限があっても「ID/PWを与えられたユーザーが複数人いる場合、送信可能化権を侵害し得る」と判断されました。本件では人数が50名超〜70名ほどのログイン権限者がいたため、多数の者への送信可能状態となり、公衆送信権の侵害と認定。
-
開発途中のファイルを任意に改変して機能追加した行為が「翻案・同一性保持権の侵害」に及ぶとされた点も注目されます。著作権法47条の3(プログラムの所有者による必要範囲での改変)を超えた改変と判断されました。単なるバグ修正や動作調整ではなく、大幅な機能追加は「著作権者の同意が必要」になる可能性が高いことが示唆されます。
-
-
不当利得の額認定
-
原告は多額の請求(委託費用・慰謝料など)をしたものの、「著作者人格権侵害では被告が金銭的な利得を受けたとはいえない」という考え方により退けられ、また「委託費用相当額」はそもそも契約未成立として否定されました。
-
結局、侵害行為に対する利用料相当額として20万円のみ認められた判決となったのです。こうした金額評価は、開発途中のシステムやプログラムをどの程度「実用・活用」できていたか、被告学園が支払った他の費用(105万円)等の事情から総合的に判断されたと推察されます。
-
-
センター側の関与否定
-
本件では、原告は「被告センターも共同で侵害に関わった」と主張しましたが、具体的な侵害行為への指示や黙示の同意を立証できず、裁判所は不法行為責任を否定。
-
実際のプログラム利用・改変を行ったのは学園サイドであり、センターは発注者・事業主体として包括的に学園に依頼していたに過ぎないという整理がなされています。
-
5 結論と学び
最終的に、知財高裁判決は地裁判決と同様に、原告の請求を一部(20万円+遅延損害金)だけ認容し、その余を棄却しました。そして被告学園の主張(著作権は取得済みとする主張や20万円すら払わないとする附帯控訴)も退けられました。
本件は、教育機関が海外の教育支援事業を委託された場面で、多数のステークホルダー(学園・センター・開発者・海外研修所)が関わったため、契約や権利関係が曖昧になったことが根本にあります。また、「職務著作」と思い込み、契約書を交わさず開発を進めてしまう事例は教育・研究機関に限らず散見されます。著作権帰属をめぐる紛争予防には、開発の初期段階で契約書を取り交わすことが不可欠であると再確認できるでしょう。
また、著作権侵害については、プログラムの所有者や利用者が「自分に権利があるはずだ」と安易に判断して勝手に改変・配布等を行うと、翻案権や同一性保持権の侵害となり得ること、人数限定でもウェブ上にアップすれば公衆送信権侵害となるリスクがある点も本判決は示唆しています。
もっとも、原告が得られた金額は結果的に20万円に留まり、「侵害された側としては必ずしも十分とはいえない救済」とも見えます。侵害行為と原告の損失との因果関係、あるいは被告の利得額の立証は、想像以上に厳格に判断されることがわかります。今後の開発委託やコラボレーションにおいては、契約書で対価と著作権帰属を明確にし、万が一トラブルになった場合の係争リスクを下げる努力が不可欠です。