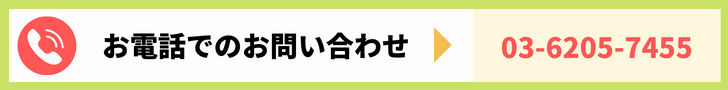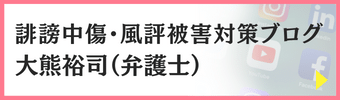はじめに
ビジネスの世界では、ヒット商品の登場と共に、類似品や模倣品をめぐるトラブルが後を絶ちません。特に、かつてのビジネスパートナーが競合相手となるケースは、法的に複雑な問題を生じさせます。
今回解説するのは、ペット用健康補助食品「ワンスプーン」の販売をめぐり、製造元(原告:ホワイトスター株式会社)が、元・独占販売代理店(被告:株式会社アトラス)を訴えた事件です。
被告は、原告との販売契約が終了した直後、非常によく似た名称の「ワンスプーンプレミアム」という自社商品を、原告が使っていたネットショップのページを流用する形で販売し始めました。
一審の大阪地方裁判所(令和5年9月14日判決・裁判所ウェブサイト)は、原告の請求を全面的に棄却しましたが、控訴審の大阪高等裁判所(令和6年5月31日判決・裁判所ウェブサイト)は判断を覆し、被告の行為を「自由競争の範囲を逸脱した」不法行為であると認定し、損害賠償を命じました。
なぜ、一審と控訴審で判断が分かれたのでしょうか? 不正競争防止法では保護されなかった原告が、なぜ民法の不法行為で済されたのでしょうか? そして、商標権さえ取れば、何をしても許されるのでしょうか?
この判決は、ECサイトでの販売が主流となった現代において、メーカーと販売代理店の関係、顧客の奪い合い、そして「ビジネス上の信義」とは何かについて、多くの重要な示唆を与えてくれます。本稿では、この事件の経緯から両審級の判断、そして実務上の教訓までを徹底的に掘り下げていきます。
1. 事件の背景:信頼から対立へ
本件の登場人物と、トラブルに至るまでの経緯を整理します。
-
控訴人(原告):ホワイトスター株式会社
ペット用健康補助食品「ワンスプーン」(以下、原告商品)の製造販売元。代表者はP1氏 。
-
被控訴人(被告):株式会社アトラス
健康関連商品などを手掛ける会社 。本件では、原告商品の元・独占販売代理店。
-
関係者:有限会社フェイス
紳士服等の製造小売業者 。代表者のP3氏は、原告代表P1氏と被告の事業推進部長P2氏の双方と面識があり、本件の取引を仲介した。
(1) 「ワンスプーン」の誕生と消えた商標権
原告商品「ワンスプーン」は、LBSという免疫賦活物質を原材料とするペット用サプリメントです 。もともとは、株式会社緑微研という会社が開発・製造し、「ワンスプーン」の名称で商標権(本件商標権1)も保有していました。
しかし、この商標権1は、平成29年(2017年)11月に更新登録がされず、期間満了により消滅してしまいます 。これは、本件の重要な伏線となります。
その後、令和元年(2019年)7月、P1氏が代表を務める原告(ホワイトスター社)が、緑微研からこの商品の製造販売事業を引き継ぎました。
(2) 独占販売契約の締結と蜜月
事業を引き継いだものの、販路に課題を抱えていた原告。ここで登場するのが、仲介役のフェイス社P3氏です。P3氏が被告(アトラス社)に原告商品を紹介したことをきっかけに、両社は急接近します。
そして令和元年9月、原告と被告は以下の内容を主とする販売契約(本件販売契約)を締結しました。
-
原告は、被告に原告商品を卸売販売する。
-
被告は、原告の販売代理店となり、インターネット等で販売する。
-
原告は、被告を独占的な販売代理店と定め、他社に原告商品を卸すことはできない。
-
契約期間は1年で、意思表示がなければ自動更新。
この契約により、被告はAmazonや楽天市場などのネットショップで原告商品の独占販売を開始。売上は順調に伸びていきました。
(3) 関係の悪化、そして裏での商標出願
しかし、蜜月関係は長くは続きませんでした。商品のパッケージ表示や販売方針をめぐり、原告代表のP1氏と、仲介役のフェイス社P3氏との間で見解が対立し、関係が悪化していきます。原告P1氏は、被告側が商品の配合率などを詮索してくることに不信感を抱くようになります。
そんな不穏な空気の中、令和2年(2020年)11月、フェイス社は、原告に知らせることなく、かつて緑微研が保有していた商標と酷似した「ワンスプーン」の商標(本件商標権2)を自社名義で出願します。この出願は、契約関係が悪化し始めていた時期に行われました。
(4) 契約終了と「ワンスプーンプレミアム」の登場
関係の溝が埋まらないまま、令和3年(2021年)8月、原告は被告に対し契約を更新しない旨を通知し、同月末をもって本件販売契約は終了しました 。
契約終了からわずか3ヶ月後の同年12月、被告は驚くべき行動に出ます。
フェイス社が登録したばかりの商標権2の使用許諾を受け、「ワンスプーンプレミアム」という名称のペット用サプリメント(被告商品)の販売を開始したのです。被告商品も、原告商品と同じ「LBS」を原材料としていました。
さらに問題だったのはその販売手法です。被告は、これまで原告商品を販売していたAmazonや楽天のネットショップページをそのまま流用し、商品名と画像を「ワンスプーンプレミアム」に差し替えただけで販売を始めたのです。そこには、原告商品に寄せられた多数の高評価カスタマーレビューが残されたままでした 。
インスタグラムでは「ワンスプーンの良さはそのままに、より食べやすく改良しました」「ONE SPOONがリニューアルしました」などと宣伝し、あたかも被告商品が原告商品の後継・改良品であるかのようにアピールしていました。
自社のブランドと顧客を奪われたと考えた原告は、被告商品の製造販売差止と500万円の損害賠償を求め、提訴に踏み切りました。
2. 争点:法廷での攻防
裁判での主な争点は以下の3つでした。
-
不正競争の成否(不競法2条1項1号):被告の行為は、原告の商品と混同させる「混同惹起行為」にあたるか?
-
不法行為の成否(民法709条):仮に不正競争でなくとも、被告の一連の行為は信義則に違反し、原告の営業権を侵害する不法行為にあたるか?
-
損害の有無とその額
(1) 原告(ホワイトスター社)の主張
-
不正競争について:「ワンスプーン」という名称は、ペットの飼い主という特定の需要者の間では十分に知られており「周知性」がある。被告は類似名称「ワンスプーンプレミアム」を使い、後継品であるかのように装い、レビューを流用するなどして混同を生じさせている。これは典型的な混同惹起行為だ。
-
不法行為について:被告には、契約終了後に販売サイトを速やかに削除すべき信義則上の義務があった。にもかかわらず、サイトやレビューを流用し、後継品であるかのように虚偽を述べて顧客を奪う行為は、原告の営業権を侵害する悪質な不法行為だ。また、フェイス社による商標登録は信義則違反であり、被告がそれを承知で利用するのも共同不法行為に等しい。
(2) 被告(アトラス社)の主張
-
不正競争について:「ワンスプーン」に周知性などない。販売実績は乏しく、ありふれた言葉の組み合わせにすぎない。仮に多少知られるようになったとしても、それは被告の販売努力の賜物であり、それを盾に原告が権利を主張するのはおかしい。
-
不法行為について:被告はフェイス社から正当な使用許諾を得て商標権を行使しているだけであり、何ら違法ではない。後継品であるかのような虚偽は述べておらず、レビューが残っていたとしても、それは宣伝目的ではない 。フェイス社による商標登録も、誰でも出願できる状態だったのだから適法だ。
3. 一審(大阪地裁)の判断:原告、全面敗訴
令和5年9月、大阪地裁は原告の請求をすべて棄却する判決を下しました 。
(1) 争点1(不正競争):「周知性」なし
裁判所は、不正競争防止法2条1項1号が成立するための大前提である「商品等表示の周知性」を否定しました。
その理由として、
「原告商品の売上げは、本件販売契約が終了する令和3年8月までの2年間で3837袋であり、その後の令和4年1月までのアマゾンでの販売数量を含めても4435袋(1袋250g)にすぎず、購入者は多くても1000人程度にとどまっている。」
と指摘。全国のペット飼育者を需要者と想定するネット販売において、この販売実績では「需要者の間に広く認識されている」とは到底言えない、と判断しました。周知性がなければ、混同もへったくれもない、というロジックです。
(2) 争点2(不法行為):違法とまでは言えない
次に、一般不法行為の成否について、裁判所は被告の一連の行為を認定しつつも、「不法行為を構成するとは認められない」と結論付けました 。
-
サイトの削除義務:契約が終わったからといって、販売ページを削除すべき信義則上の義務とまでは言えない。
-
表示やレビュー流用:後継品と誤認する可能性は認めつつも、「虚偽の事実を掲載したとまでは認められない」。レビューの件数もそれほど多くなく、意図的に流用したとも言えないため、「原告の営業権が侵害されるとは考え難い」とした。
-
商標権の利用:フェイス社による商標登録は、原告が自ら商標管理を怠っていた側面もあり、フェイス社に不正の目的があったとまでは言えない。そのため、これを被告が利用することも違法ではない。
結果として、原告の主張はすべて退けられ、全面敗訴となりました。この判決に対し、原告は控訴します。
4. 控訴審(大阪高裁)の判断:逆転勝訴!
令和6年5月、大阪高裁は一審判決を一部変更し、被告の不法行為を認定。被告に対し、20万円の損害賠償を命じる逆転判決を下しました 。
なぜ、高裁は一審と異なる結論に至ったのでしょうか。その判断の核心に迫ります。
(1) 争点1(不正競争):一審判断を維持
まず、不正競争の成否については、高裁も一審の判断を支持。「ワンスプーン」の周知性は認められないとして、不競法に基づく請求は退けました。ここまでは一審と同じです。
(2) 争点2(不法行為):自由競争の範囲を逸脱した「違法な販売態様」
本件のハイライトは、ここからです。高裁は、不正競争に該当しないとしても、被告の行為全体を評価し、「自由競争の範囲を逸脱した違法な販売態様で控訴人の顧客を奪っているものといえるから不法行為を構成する」と断じました。
高裁が「違法」と判断したポイントは、以下の3点に集約されます。
① 行為態様の悪質性:需要者の誤認を積極的に利用
高裁は、被告の一連の行為を「需要者の誤認を利用するもの」と強く非難しました。
-
サイト閉鎖を告知しながら、実際には原告の販売ページを流用し、被告商品のページに作り替えたこと。
-
その際、原告商品の高評価レビューを残したままにしたこと。
-
「プレミアム」という名称に加え、「リニューアル」「改良しました」といった表示を用いることで、積極的に原告商品の後継・改良品であると誤信させようとしたこと。
これらの行為を個別にではなく一体として捉え、その全体が悪質であると評価したのです。
② 顧客の帰属:「被告の顧客」ではなく「原告の顧客」
被告は「ネット販売で顧客を開拓したのは自分たちなのだから、その顧客は被告の顧客だ」と主張しました。これに対し、高裁は非常に興味深い判断を示します。
「原告商品が...リピート購入されるようになったとすれば、それは原告商品がペットにとってよい商品であったという実体験がその購入者にあったからと考えるのが自然であり...原告商品に対する信頼は、販売取扱者である被控訴人に対するものというより原告商品自体に向けられるものというべきであるから...それらの者は、原告の顧客であるというべきである」
つまり、商品の魅力によってリピート購入する顧客は、販売サイトを運営する代理店の顧客ではなく、商品を製造したメーカーの顧客である、と認定したのです。この認定により、被告の行為は「他者(原告)の顧客を、誤認を利用して違法に奪う行為」であると明確に位置づけられました。
③ 商標権の行使:権利の濫用を許さない
被告の「フェイス社から許諾を得た正当な権利行使だ」という最後の砦も、高裁は打ち砕きました。裁判所は、商標出願に至る経緯を重視します。
-
原告と被告の関係が悪化し始めた時期に原告に秘密のままフェイス社が商標出願を行ったこと
これらの事実から、高裁は「フェイスは、被控訴人と共謀し、本件販売契約が終了した後に...被控訴人が開設したインターネットのサイトに原告商品を求めてアクセスしてくる顧客との関係をそのまま維持して利益を確保することを目論んでいたものと推認するのが相当」と、両社の悪意ある意図にまで踏み込んで推認しました 。
そして、このような動機で取得され、需要者の誤認を招くような形で使われる商標権の行使は、商標法の目的にも反するものであり、その違法性は阻却されない(=言い訳にはならない)と結論付けました 。
(3) 争点3(損害額):20万円を認定
高裁は、被告の不法行為によって原告が逸失利益の損害を被ったと認定しました。ただし、原告が主張した500万円は経費などを考慮しておらず認められないとし、原告の利益率(1袋あたり約400円との供述)、被告の販売拡大への寄与、契約終了後の原告の販売体制などを総合的に考慮し、損害額を20万円と算定しました。
5. この判決から学ぶべきこと:実務への示唆
この一審と二審で判断が分かれた事件は、現代のビジネス、特にECビジネスに関わるすべての事業者にとって示唆に富んでいます。
(1) 不正競争の「周知性」の壁は依然として高い
まず、不競法で保護されるための「周知性」のハードルは、ネット販売の時代においても依然として高いことが確認されました。全国の消費者がアクセス可能な市場では、数千個程度の販売実績では「広く認識されている」とは認められにくいのが現実です。自社のブランドを法的に守るためには、相当程度の販売実績や広告宣伝の客観的な証拠を積み重ねる地道な努力が不可欠です。
(2) 不正競争でダメでも「不法行為」で救済される道がある
本件の最大の教訓は、不正競争という構成が取れなくても、一般不法行為(民法709条)によって救済される可能性があることを示した点です。高裁は、個別の行為が形式的に適法に見えても、その連なりや全体の態様、当事者間の関係性などを総合的に評価し、「自由競争として許される範囲」を超えているかどうかを判断しました。
特に、
-
元取引先の販売チャネルや顧客レビューの流用
-
後継品や改良品であるかのような積極的な誤認の誘発
といった行為は、たとえ商品名が不競法上の「周知」表示でなくても、「信義則に反する違法な行為」と評価されるリスクが極めて高いと言えるでしょう。
(3) 商標権は「魔法の杖」ではない
「商標さえ取ってしまえば、その名前を独占できる」と考えるのは早計です。本判決は、商標権の取得経緯や行使の態様が問われることを明確にしました。
特に、取引関係にあった相手方の信用にタダ乗りする(フリーライド)目的や、相手方を妨害する目的で出願されたと疑われるような商標権の行使は、裁判所によって厳しく制限される可能性があります。権利を持っているからといって、それが常に正義とは限らないのです。この判断は、ビジネス上の信義を軽視した権利取得・行使に警鐘を鳴らすものとして、非常に重要です。
(4) 【メーカー・製造元の方へ】自衛策の徹底を
商標管理は生命線:自社のブランド名や商品名は、必ず商標出願し、権利を確保してください。そして、存続期間の管理を徹底し、更新を絶対に忘れないでください。本件は、商標権の消滅がトラブルの大きな引き金となりました。
-
契約書で縛る:販売代理店との契約書には、契約終了後の競業避止義務、顧客情報や販売ページの取扱い、知的財産権の帰属などを、可能な限り明確に定めておくべきです。特に、契約終了後のウェブページの閉鎖やレビューの削除義務などを具体的に盛り込むことが、後の紛争予防につながります。
(5) 【販売代理店・小売業者の方へ】越えてはいけない一線
-
清算はクリーンに:取り扱いを終了した商品の販売ページやレビューを、後続の類似商品に流用する行為は極めて危険です。たとえシステム上可能であっても、倫理的に、そして法的に許されない行為と判断されるリスクがあります。新たな商品を売るなら、新たなページで、ゼロから評価を積み上げるのが王道です。
-
信義を重んじる:元取引先の信用を利用しようとする安易な考えは、最終的に大きな代償を払うことになりかねません。たとえ自社で商標を確保したとしても、その背景に裏切りや不誠実な動機があれば、権利の行使は認められない可能性があります。公正な競争こそが、ビジネスを長続きさせる鍵です。
まとめ
「ワンスプーン」をめぐるこの事件は、一審と控訴審で判断が分かれるという劇的な展開をたどりました。高裁判決は、不正競争防止法の要件を満たさないグレーな行為に対しても、民法上の不法行為という枠組みで「待った」をかけることができる可能性を示しました。それは、法律の条文を形式的にクリアするだけでなく、ビジネスにおける「公正さ」や「信義」といった、より根源的な価値を裁判所が重視した結果と言えるでしょう。
ECプラットフォームがビジネスの主戦場となった今、顧客データやレビューといった無形の資産の価値はますます高まっています。それらを誰が、どのように利用できるのか。本判決は、その境界線を考える上で、すべてのビジネスパーソンにとって必読のケーススタディと言えます。