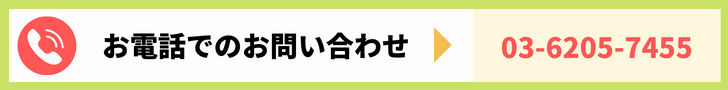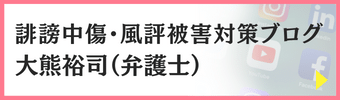「著作権がない」は自由の証か?北朝鮮映画事件が示すコンテンツ利用の落とし穴
はじめに:法が保護しないコンテンツをめぐる根源的な問い
インターネットが社会インフラとなり、誰もが情報の発信者・受信者となった現代において、「コンテンツの利用」は日常的な行為となりました。その際、多くの人がまず気にするのが「著作権」の存在です。では、もし「著作権がない」あるいは「著作権法で保護されない」と判断されたコンテンツがあった場合、それは誰でも、どんな目的でも、完全に自由に利用できる「無法地帯」なのでしょうか。
この根源的な問いに、一つの重要な指針を示したのが、2011(平成23)年12月8日に最高裁判所が下した、通称「北朝鮮映画事件」の判決(裁判所ウェブサイト)です。この事件は、日本のテレビ局が「北朝鮮で制作された映画」をニュース番組で無断放送したことから始まりました。争点は、そもそも日本の著作権法がこの映画を保護するのか、そして、仮に保護しないとしても、テレビ局の行為は別の法律(民法の不法行為)で許されないのではないか、という二点に集約されました。
最終的に最高裁判所は、「この映画は日本の著作権法では保護されない」かつ「今回のケースでは不法行為にも当たらない」という結論を下しました。しかし、この判決の真の重要性は、結論そのものよりも、そこに至る詳細な論理と、将来の類似紛争に適用されうる判断の枠組みを提示した点にあります。特に、「著作権法で保護されない利用行為が、例外的に一般不法行為を構成する『特段の事情』」という概念に言及したことは、実務に大きな影響を与えました。
この記事では、法律の専門家でないWebサイト運営者、クリエイター、企業の法務・知財担当者、そして法律を学ぶ学生の方々にもご理解いただけるよう、徹底的に解説します。
事件の背景から最高裁判決に至るまでの詳細な経緯(一審・二審の判断を含む)
「国家承認」と「条約」をめぐる国際私法上の論点
著作権法(特別法)と民法(一般法)の関係性という法理論の核心
判決が私たちのビジネスや創作活動、情報発信に与える具体的な影響と、今後注意すべき法的リスク
この判決を深く理解することは、デジタル時代のコンテンツ利用における法的リテラシーを高め、予期せぬトラブルを回避するための確かな道標となるはずです。
第1:事件の全貌 ― なぜ北朝鮮の映画が日本の最高裁で争われたのか
1. 登場人物と契約関係
この事件の中心には、3つのプレイヤーが存在します。
原告 X2(朝鮮映画輸出入社): 北朝鮮の文化省傘下にある行政機関。北朝鮮の国内法に基づき、1978年に制作された2時間を超える長編劇映画(以下「本件映画」)を含む、複数の映画の著作権を有するとされていました。
原告 X1(カナリオ企画): 日本の企業。2002年9月、原告X2との間で「映画著作権基本契約」を締結しました。この契約により、X1社は本件映画などについて、日本国内における独占的な上映、放送、および第三者への利用許諾といった権利を付与されました 。X1社は、これらの映画を日本でビジネス展開しようとしていたのです。
被告 Y社(株式会社フジテレビジョン): 日本を代表するテレビ放送事業者です 。
2. 国際情勢と日本政府の対応
この単純に見える契約関係に、国際政治の現実が影を落とします。
2003年1月28日、北朝鮮は「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託し、同年4月28日に同条約の効力が北朝鮮について生じました。ベルヌ条約は著作権保護に関する最も基本的な国際条約であり、加盟国の国民の著作物は、他の加盟国でも自国民の著作物と同様に保護されるのが原則です(内国民待遇の原則)。
しかし、日本政府は北朝鮮を国家として承認していませんでした。この「国家の未承認」という事実が、法解釈の根幹を揺るがします。ベルヌ条約の効力が北朝鮮で生じる直前の2003年4月22日、日本の文化庁は「わが国は北朝鮮を国家として承認しておらず、北朝鮮のベルヌ条約加入により、わが国が北朝鮮の著作物を保護すべき義務を負うわけではない」という公式見解を発表しました。外務省や文部科学省も、日本はベルヌ条約に基づき北朝鮮国民の著作物を保護する義務を負うとは考えていない、との立場を一貫して示していました。
3. 問題となった放送行為
こうした複雑な状況下で、事件の引き金となる放送が行われます。
2003年12月15日、被告Y社は夕方のニュース番組「スーパーニュース」内で、約6分間の特集企画を放送しました。この企画の目的は、「北朝鮮における映画を利用した国民に対する洗脳教育の状況を報ずる」という報道目的でした。
番組では、本件映画の主演女優が制作の思い出を語るインタビュー映像と、本件映画の映像そのものを組み合わせる形で構成されていました。この中で、合計2分8秒間、本件映画の映像が、原告X1およびX2の許諾なく使用されたのです。
4. 訴訟の提起と請求内容
これに対し、原告X1とX2は共同でY社を提訴しました。彼らの主張は二段構えでした。
主位的請求(メインの主張): 北朝鮮がベルヌ条約に加盟した以上、本件映画は日本の著作権法6条3号にいう「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」に該当する。したがって、Y社の無断放送は、X2が有する公衆送信権(放送する権利)と、X1が有する日本国内での独占的利用権を侵害する著作権侵害である。Y社に対し、今後の放送の差止めと、損害賠償を求めました。
予備的請求(サブの主張): 控訴審から追加された主張です。仮に、本件映画が著作権法で保護されないとしても、Y社の無断放送は、我々が本件映画について有する「法的保護に値する利益」を違法に侵害するものであり、民法709条に基づく一般不法行為が成立する。Y社は、それによって生じた損害を賠償する責任を負う、と主張しました。
こうして、国家承認という国際政治マターと、著作権という知的財産権、そして不法行為という民法の一般原則が交錯する、複雑な法廷闘争の幕が切って落とされたのです。
第2:裁判の経過ー地裁・高裁・最高裁の判断の変遷
最高裁判決の意義を深く理解するためには、そこに至るまでの下級審(第一審・第二審)の判断を知ることが不可欠です。特に、第二審の知財高裁は最高裁と異なる結論を導き出しており、両者を比較することで、法的な論点がより明確になります。
1. 第一審・東京地方裁判所の判断(請求棄却)
2007年12月14日、東京地裁は原告らの請求を全面的に退ける判決を下しました 。
判決の核心は、争点1、すなわち「本件映画が日本の著作権法で保護されるか」という点に絞られました。東京地裁は、日本政府が北朝鮮を国家として承認しておらず、ベルヌ条約上の権利義務関係の発生を否定しているという事実を重視しました。そして、「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」とはいえないと結論付け、著作権侵害を前提とする主位的請求は理由がないとしました。この時点では予備的請求がなされていなかったため、判決はこれで終了しました。
2. 第二審・知的財産高等裁判所の判断(一部認容)
原告らはこの判決を不服として控訴。控訴審の舞台となった知的財産高等裁判所(知財高裁)で、原告らは前述の「予備的請求(一般不法行為の主張)」を追加しました 。
2008年12月24日、知財高裁は驚くべき判断を下します 。
著作権保護(主位的請求)について: 知財高裁は、東京地裁の判断を踏襲しました。すなわち、日本が北朝鮮を国家承認していない以上、ベルヌ条約に基づく保護義務は負わないとし、本件映画は著作権法6条3号の著作物には該当しないと判断しました。この点において、原告らの主位的請求は再び退けられました。
一般不法行為(予備的請求)について: ここからが知財高裁の独特な判断でした。知財高裁は、著作権法による保護が否定されても、直ちに民法による保護まで否定されるわけではない、と考えたのです。 そのロジックは以下の通りです。
本件映画は客観的に経済的価値を持つ財産である。
原告X1は、契約によって日本国内で本件映画を独占的に利用し、利益を享受する権利を得ている 。これは法律上保護に値する利益である。
被告Y社は、営利目的の放送事業者でありながら、許諾を得ることなく無断で本件映画を放送し、X1の利益を違法に侵害した。この行為は社会的な相当性を欠く。
したがって、Y社の行為は、原告X1に対する一般不法行為(民法709条)を構成する。
この知財高裁の判決は、「著作権法で保護されない情報やコンテンツであっても、その利用態様によっては一般不法行為が成立しうる」という道を開いた点で、非常に注目を集めました。しかし、この判断は、次の最高裁で覆されることになります。
3. 最高裁判所の判断(破棄自判・請求棄却)
この知財高裁判決に対し、敗訴部分のある原告らと被告Y社の双方が上告。そして2011年12月8日、最高裁判所第一小法廷は最終判断を下しました 。
最高裁は、知財高裁の判決のうち、一般不法行為の成立を認めた部分を破棄し、原告X1の請求を棄却しました。これにより、原告らの請求は全面的に退けられ、被告Y社の完全勝訴が確定したのです。
最高裁がなぜ知財高裁と異なる結論に至ったのか。その詳細なロジックこそ、この判決の核心であり、次章で詳しく見ていきます。
第3:最高裁判決の法理ーなぜ不法行為は成立しなかったのか
最高裁判決は、大きく二つの柱で構成されています。一つは「著作権保護の否定」、もう一つは「一般不法行為の否定」です。後者のロジックは、今後のコンテンツ利用実務に極めて重要な示唆を与えています。
1. 著作権保護の否定 ― 国家承認と条約の壁
まず、最高裁は知財高裁と同様に、本件映画は日本の著作権法で保護されないと結論付けました 。その論理構成は以下の通りです。
一般論の提示: 我が国について既に効力が生じている多数国間条約に、我が国が承認していない国(未承認国)が事後に加入した場合、我が国とその未承認国との間に直ちに条約上の権利義務関係が生ずるわけではない。我が国は、その未承認国との間で権利義務関係を発生させるか否かを選択できるのが原則である。
例外の検討: ただし、その条約が「普遍的価値を有する一般国際法上の義務」を定めるものである場合は例外となる。
ベルヌ条約へのあてはめ: ベルヌ条約は、加盟国の国民の著作物を保護する一方で、非加盟国の国民の著作物は原則として保護しないなど、加盟国という国家の枠組みを前提としている。したがって、これは「普遍的価値を有する一般国際法上の義務」を課すものではない 。
日本の意思の確認: そして、日本政府は、北朝鮮の加入に際して効力発生の告示を行っておらず、一貫して保護義務を負わないとの見解を示している。これは、日本が北朝鮮との間でベルヌ条約上の権利義務関係を発生させないという立場を採っていることを明確に示している 。
結論: 以上のことから、日本はベルヌ条約に基づき北朝鮮国民の著作物を保護する義務を負わず、本件映画は著作権法6条3号の著作物には当たらない。
2. 一般不法行為の否定 ―「特別法」と「一般法」の峻別
ここからが、この判決の真骨頂です。最高裁は、知財高裁が認めた一般不法行為の成立を、なぜ否定したのでしょうか。その鍵は、「著作権法(特別法)」と「民法(一般法)」の関係性の捉え方にあります。
最高裁は、まず著作権法の役割について、以下のように定義しました。
「著作権法は、著作物の利用について、一定の範囲の者に対し、一定の要件の下に独占的な権利を認めるとともに、その独占的な権利と国民の文化的生活の自由との調和を図る趣旨で、著作権の発生原因、内容、範囲、消滅原因等を定め、独占的な権利の及ぶ範囲、限界を明らかにしている。」
これは、著作権法が単に権利を保護するだけでなく、「保護する範囲」と「保護しない範囲」を意図的に線引きすることで、権利者の利益と、社会全体の利益(自由な文化発展)のバランスを取っている法律なのだ、という考え方です。著作物を保護するか否かを定める著作権法6条も、まさにその線引きのための規定であるとしました
この考え方を前提に、最高裁は決定的な判断枠組みを示します。
「ある著作物が同条各号所定の著作物に該当しないものである場合、当該著作物を独占的に利用する権利は、法的保護の対象とはならないものと解される。したがって、同条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は、同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」
この一文に、最高裁のロジックが凝縮されています。分かりやすく分解すると、以下のようになります。
原則(不法行為は成立しない): 著作権法が「保護しない」と定めた著作物について、その「利用から得られる利益(=著作権法が規律しようとしている利益そのもの)」が侵害されたと主張しても、それは法的に保護されない。なぜなら、著作権法は意図的にそこを保護の対象外と定めているからである 。著作権法で保護されないものを、安易に民法の不法行為で救済することは、著作権法が定めたバランスを崩してしまうことになる。
例外(不法行為が成立する場合): ただし、その利用行為が、「著作権法が規律する利益とは“異なる”利益」を侵害した場合は話が別である。例えば、他人の営業活動を不当に妨害する「営業妨害」や、他人の名誉を傷つける「名誉毀損」などがこれにあたりうる。このような「特段の事情」があれば、一般不法行為が成立する余地は残されている。
3. 本件へのあてはめ:なぜ「特段の事情」は認められなかったか
最高裁は、この枠組みを本件に適用しました。
まず、原告X1が主張する「本件映画を利用することにより享受する利益」は、まさに著作権法が規律の対象とする「独占的な利用の利益」そのものであると指摘。したがって、本件映画が著作権法で保護されない以上、この利益が侵害されても不法行為にはならないとしました。
次に、例外である「特段の事情」の有無を検討します。最高裁は、原告の主張を「営業妨害による営業上の利益侵害」と解釈できる可能性に触れつつも、以下の事実から、営業妨害には当たらないと判断しました。
目的の正当性: 本件放送は、テレビニュース番組において、北朝鮮の国家の現状等を紹介するという報道目的で行われたものである。
利用態様の相当性: 2時間を超える長編映画のうち、放送で利用されたのは合計わずか2分8秒にすぎない。
結論: これらの事情を考慮すれば、本件放送が「自由競争の範囲を逸脱し、X1の営業を妨害するものであるとは到底いえない」。
以上から、本件には不法行為が成立するための「特段の事情」は存在しないと結論付け、知財高裁の判決を覆したのです。
第4:この判決から学ぶべきこと ― 実務への影響と今後の課題
この最高裁判決は、法律の専門家だけでなく、コンテンツを扱うすべての実務家にとって示唆に富むものです。
1. 「特別法と一般法の関係」という基本原則の再確認
本判決の最大の意義は、知的財産法(特別法)と民法(一般法)の関係について、明確な指針を示した点にあります。知的財産法が、政策的な考慮に基づき、権利保護の範囲を意図的に限定している場合、その枠外にある行為について、安易に民法の一般不法行為を適用して保護すべきではない、という考え方です。これは、立法府(国会)が定めた精緻な利益調整を、司法府(裁判所)が安易に覆すべきではない、という司法の謙抑的な姿勢の表れともいえます。
この考え方は、著作権法6条(保護される著作物の範囲)に限らず、著作権法の他の条項にも応用できます 。例えば、
権利の目的とならない著作物(憲法、法令、判決など)の利用
保護期間が満了した著作物の利用
権利制限規定(私的複製、引用など)に該当する利用
アイデアや事実にすぎないものの利用
これらのケースでは、著作権法が明確に「自由な利用」を許容しているため、原則として一般不法行為の成立も否定される可能性が高いと考えられます 。
2. 「特段の事情」=不法行為成立の余地を探る
しかし、本判決はすべての道を閉ざしたわけではありません。「特段の事情」があれば不法行為が成立する余地を残した点が、もう一つの重要なポイントです 。では、どのような場合が「特段の事情」にあたるのでしょうか。
本判決が例示したのは「営業妨害」でした 。これは、他人の事業活動に対して、社会的に許容される競争の範囲を逸脱した手段・方法で不当な損害を与える行為を指します。本件では報道目的のごく一部の利用だったため否定されましたが、仮にY社が、
本件映画の全編をそのまま無断で放送・配信した(いわゆるデッドコピー)
原告X1が計画していたDVD発売の直前に、映画を違法アップロードしてビジネスを妨害した
といったケースであれば、「自由競争の範囲を逸脱」したとして、営業妨害にあたる可能性は十分に考えられます。
このほかにも、他人の商品やサービスであるかのように見せかける「混同惹起行為」や、他人の信用を傷つける「信用毀損行為」(これらは不正競争防止法でも規制されています)などが、「特段の事情」に該当しうると考えられます 。
3. クリエイター・事業者がとるべきアクション
この判決を踏まえ、実務家はコンテンツ利用に際して、より多角的な視点を持つ必要があります。
ステップ1:著作権の有無の確認 これは基本中の基本です。保護される著作物か、保護期間は満了していないか、権利制限規定に該当しないかを確認します。
ステップ2:「著作権法以外の法的リスク」の検討 たとえ著作権クリアランスが不要なコンテンツであっても、思考を停止してはいけません。「その利用はフェアか?」という視点から、一般不法行為のリスクを検討する必要があります。
利用の目的は正当か?(報道、研究、批評か、単なる便乗か)
利用の態様は相当か?(必要最小限の利用か、丸ごとの利用か)
他人のビジネスに与える影響は?(競業者の営業を不当に害していないか)
他人の信用や名誉を毀損していないか?
これらの点を総合的に考慮し、少しでも「やり過ぎ」と感じる場合は、利用を控えるか、専門家に相談するのが賢明です。
4. 残された課題:判断基準の明確化
本判決は重要な枠組みを示しましたが、すべてを解決したわけではありません。最大の課題は、「どのような行為が『自由競争の範囲を逸脱した営業妨害』にあたるのか」という具体的な判断基準が、依然として明確ではない点です。この基準は、今後の裁判例の積み重ねによって、徐々に形成されていくものと考えられます。事業者としては、常に最新の判例動向を注視していく必要があります。
まとめ:法の境界線を歩くための羅針盤として
「北朝鮮映画事件」最高裁判決は、国際関係、著作権法、民法が複雑に絡み合った難解な事件でしたが、その判示するところは、現代のコンテンツ社会を生きる私たちにとって普遍的な教訓を含んでいます。
本判決の要点を改めて整理します。
著作権法の保護範囲は絶対ではない: 国際条約があっても、国家間の承認関係など、政治的な現実によってその適用範囲は左右されることがある。
著作権法は利益調整の法律である: 著作権法が「保護しない」と定めていることには、「自由な利用を保障する」という積極的な意味がある。そのため、保護されない著作物の利用は、原則として不法行為にもならない。
自由には「公正さ」という制約が伴う: ただし、その自由は無制限ではない。他人の正当な営業努力にタダ乗りするような、社会的に見て「やり過ぎ」な利用(自由競争の範囲の逸脱)は、「特段の事情」として一般不法行為を構成するリスクがある。
私たちは、コンテンツを利用する際、著作権法という地図だけに頼るのではなく、その地図の外側に広がる「不法行為」という広大な領域の存在を常に意識しなければなりません。本判決は、その危険な領域に踏み込まないための、そして法の境界線を慎重に歩くための、極めて重要な羅針盤を示してくれたといえるでしょう。
参考記事
この記事で解説した「北朝鮮映画事件」について、別の視点からの分かりやすい解説にご興味のある方は、以下の記事もあわせてご覧になることをお勧めします。