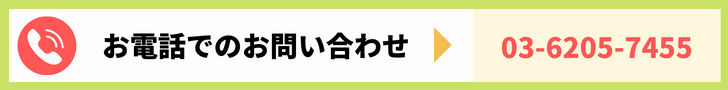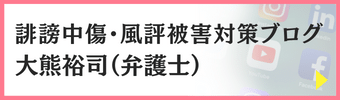著作権の利用の「裁定による利用権の設定」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
我が国の著作権法では、著作権者の利用許諾が得られない場合であっても、一定の要件を満たす場合は、裁定による著作物の利用を認めています。具体的には、以下の3つがあります。
①著作権者不明等の場合における著作物の利用(67条)
我が国の著作権法は無方式主義を採用しておりますので、商標権のように登録原簿から権利者の連絡先を突き止めるようなことはできませんので、著作物を利用するために相当の努力をしても、著作権者が不明であったり、著作権者と連絡がつかなかったりということが有り得ます。そこで、著作権法67条で「公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。」と規定されています。
「公表された著作物」に限定されているのは、著作者には公表権がありますので、未公表の著作物について裁定で利用できるようにするは妥当ではないからです。
「通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託」させるのは、著作権者の経済的な利益を保護するためです。
また「相当な努力」(法第67条第1項,同第103条,令第7条の7,告示第1条から第3条)。については、文化庁の「裁定の手引き」に記載がされておりますので、詳細を知りたい方は下のリンクからご確認下さい。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/pdf/saiteinotebiki.pdf
②著作物の放送(68条)
第68条は、公表された著作物について放送したいが、著作権者との交渉できないような場合のための規定です。条文は、「公表された著作物を放送しようとする放送事業者は、その著作権者に対し放送の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、その著作物を放送することができる。」となっています。
「公表された著作物」に対象が限定されていること、又「通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金」を支払うことを条件としているのは、第67条と同様の理由によるものです。
③商業用レコードへの録音等(第69条)
第69条は、日本国内で最初に発売がなされた商業用レコードで最初の販売の日から3年を経過しているものについて、他のレコードに録音をして販売したいようなときに、著作権者との交渉がうまくいかなかった場合に裁定により利用ができるというものです。
条文では、「商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。」となっています。
日本においては、作詞家・作曲家はレコード会社等と専属契約を結んでいることが多く、このことが音楽の流通の円滑化の妨げになっている側面があるので、裁定によって利用の円滑を図ろうとするための規定です。