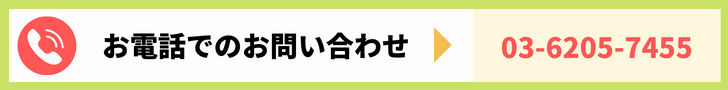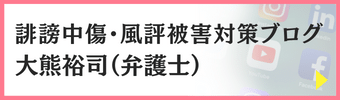第1 事案の概要
1 事実関係
原告は、本件各競走馬を所有し、又は所有していた者ら(馬主)です。被告は、ゲームソフトの製造販売を業とする株式会社(テクモ株式会社)です。
被告は、原告らの承諾を得ないで、原告らが所有等する競走馬の名称を使用した家庭用及び業務用の競馬ゲームソフト(商品名「ギャロップレーサー」、「ギャロップレーサーⅡ」。以下「本件各ゲームソフト」といいます)を製作し、販売しました。
本件各ゲームソフトは、プレイヤーが騎手(ジョッキー)となり、登録されている競走馬の中から選択した馬に騎乗し、実在の競馬場を模した画面でレースを展開するという内容のものです。登録されている競走馬の名称は、ほとんどが実在の競走馬の名称でした。被告は、家庭用ゲームソフトのパッケージ裏面やパンフレットにおいて、「実在の競走馬が1000頭以上も登場」などと記載し、実在馬名を使用していることを宣伝していました。
原告らは、被告が本件各競走馬の名称等を無断で使用した行為は、競走馬の名称等が有する顧客吸引力などの経済的価値を排他的に支配する財産的権利(いわゆる「物のパブリシティ権」)を侵害するものであると主張して、被告に対し、本件各ゲームソフトの製作、販売等の差止め及び不法行為に基づく損害賠償を請求する本件訴訟を提起しました。
2 争点
本件の主要な争点は、以下の点です。
(1)競走馬の馬名等について、いわゆる「パブリシティ権」が認められるか(権利の性質、内容、成立要件及び存続期間)
ア 原告らの主張
パブリシティ権は人に限らず、有名な「物」(本件各競走馬)についても認められるべきであると主張しました。競走馬の所有者(原告ら)は、当該競走馬の馬名等が有する顧客吸引力から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利(パブリシティ権)を有するとしました。この権利は、競走馬が死亡したり他に譲渡されたりした後でも、顧客吸引力が継続する限り、元の所有者に帰属すると主張しました 。
イ 被告の主張
パブリシティ権は「著名人」の氏名・肖像について生じるものであり、「人」でない「馬」の名前について発生することはあり得ないと反論しました。馬名の保護は商標法や不正競争防止法によって対応すべきであるとしました。仮に何らかの権利が認められるとしても、それは所有権に付随するものであり、競走馬の死亡や譲渡によって所有権が消滅すれば、その権利も同時に消滅すべきであると主張しました。
(2)本件各ゲームソフトにおける馬名等の使用がパブリシティ権を侵害するか
ア 原告らの主張
本件各ゲームソフトは、実在の競走馬の馬名等を使用することによりリアリティを持たせ、商品価値を高め、顧客吸引力を有するに至っていると主張しました。被告自身も、別件契約において一部の馬主に対し馬名の使用許諾料を支払っており、馬名の権利性を自ら認めているとしました。GIレースでの勝ち星がない馬であっても、マスコミ等で知られればパブリシティ権は獲得され得るものであると主張しました。
イ 被告の主張
本件各ゲームソフトの魅力は馬を操作するアクション性であり、馬名はリアリティを持たせるための要素に過ぎず、ゲーム内容から見れば取るに足らない役割しか果たしていないと反論しました。馬名そのものに顧客吸引力はあり得ないとし、仮に顧客吸引力が認められるとしても、GIレースの勝ち星が一つもない馬については、顧客吸引力を有しないと主張しました。
(3)差止請求の可否
ア 原告らの主張
原告らはパブリシティ権に基づき、侵害行為である本件各ゲームソフトの製作、販売等の差止めを求める権利を有すると主張しました。
イ 被告の主張
本件各競走馬の馬名は、本件各ゲームソフトのごく一部の構成要素にしか過ぎず、これを根拠にゲーム全体の製作・販売等の禁止を求めることは、権利の濫用であり許されないと主張しました。
(4)損害額
ア 原告らの主張
侵害行為により、馬名等の利用対価として得られたはずの利益(少なくとも競走馬一頭当たり金50万円)相当額の損害を被ったと主張しました。
イ 被告の主張
争う。
第2 裁判所の判断(第一審及び控訴審)
1 第一審(名古屋地裁)の判断
第一審(名古屋地判平12年1月19日)は、原告らの請求を一部認容しました。競走馬のような「物」についても、著名人(人)と同様に顧客吸引力が生じる場合があるとして、「物のパブリシティ権」の成立を認めました。そして、少なくとも「G1レースに出走したことがある馬」は顧客吸引力を有するとして、その馬名を無断使用した行為を権利侵害(不法行為)にあたると判断しました。ただし、この権利は経済的価値を保護するものに過ぎないとして、差止請求は認めず、ライセンス料相当額の損害賠償請求のみを一部認容しました。
2 控訴審(名古屋高裁)の判断
控訴審(名古屋高判平13年3月8日)も、第一審の判断の枠組みを踏襲し、「物のパブリシティ権」の成立自体は肯定しました。しかし、権利侵害が認められる範囲をより厳格にし、「G1レースに出走して優勝したことがある競走馬」に限定しました。第一審と同様に差止請求は認めませんでしたが、この基準に基づき、損害賠償の認容額を第一審よりも減額する変更判決をしました。
第3 最高裁判決の判断と意義
第一審及び控訴審がいずれも限定的に「物のパブリシティ権」の成立を肯定したのに対し、最高裁判所第二小法廷(平成16年2月13日判決・裁判所ウェブサイト)は、これを明確に否定し、原告らの請求をすべて棄却しました。以下では、その判断の要点と意義を検討します。
1 判決の要旨
最高裁は、「物の所有権は、その物の有体物としての面に対する排他的支配権能であるにとどまり、その名称等の無体的価値を排他的に支配する権能を当然に含むものではない」と判示しました。
したがって、被告が競走馬の名称をゲーム中に使用しても、競走馬という有体物の支配を妨げるものではなく、所有権の侵害には当たらないとされました。
さらに、同判決は、商標法・著作権法・不正競争防止法等の既存法体系が、それぞれ定められた要件・範囲の下で排他的権利を付与するものであり、その外に判例法によって新たな権利を創設することは、法的安定性や国民の経済活動の自由を不当に制約するおそれがあると指摘しました。
これにより、最高裁は、下級審が認めた「物のパブリシティ権」のような判例創設型の新権利を、知的財産法定主義の観点から明確に否定したものと評価されます。
2 不法行為の成否
最高裁はまた、排他的権利の存在を否定するにとどまらず、被告の行為が民法709条上の不法行為に該当するかについても、「違法とされる行為の範囲、態様等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において、これを肯定することはできない」として否定しました。
すなわち、単に顧客吸引力を利用したという事実のみでは、直ちに違法性を帯びるものではないと判断しました。
3 判決の意義
本判決は、日本におけるパブリシティ権法理の形成過程において極めて重要な位置を占めます。
すなわち、
-
「物」に関しては、法律上明文の根拠なく排他的支配を認めることはできないこと
-
所有権の効力は有体物に限られ、名称や顧客吸引力といった無体的価値には及ばないこと
を明示した点に大きな意義があります。
他方で、本判決は「人」の氏名・肖像に関するパブリシティ権については判断を示しておらず、この点は後に平成24年2月2日最高裁判決(いわゆるピンク・レディー事件)において、「人格権に由来する権利の一内容」として肯定されるに至りました。
したがって、本件は、「物」と「人」に関するパブリシティ権の法的根拠を峻別する転機となった判例と評価されます。
4 結論(下級審との比較)
第一審及び控訴審は、G1レースに出走または優勝した競走馬については限定的に顧客吸引力を認め、「物のパブリシティ権」を肯定しました。
これに対し、最高裁は、物の所有権から無体的価値への支配権を導くことを明確に否定し、判例による新たな権利の創設を回避しました。
結果として、原告らのすべての請求は棄却され、被告テクモ株式会社の勝訴が確定しました。
本判決は、知的財産権に関する権利保護の範囲を明確に限定し、判例による新たな排他権の創設には慎重であるべきとの原則を確立したものといえます。
第4 評釈(批判的検討と実務的示唆)
1 最高裁の判断枠組みの妥当性
本判決は、知的財産権法制の体系性と法的安定性を重視し、「法定主義」的立場を貫いた点で極めて妥当といえます。
もし下級審のように、法律に明文の根拠なく「物」にまでパブリシティ権を拡張してしまえば、その権利の主体・客体・存続期間・譲渡性などが不明確となり、法秩序に不測の混乱をもたらしかねません。
したがって、最高裁が新たな排他的権利の創設を慎重に回避したことは、判例としての統制力の観点から高く評価できます。
もっとも、顧客吸引力の利用による不当利得や、商業的信用の乗っ取りといった行為は、現実には競争秩序を乱す場合があります。
本判決が「違法性を否定した」ことをもって、すべての類型で自由利用が認められると解すべきではなく、今後は不正競争防止法2条1項各号の個別類型(混同惹起行為、商品等表示の冒用など)によって、事案ごとに柔軟に対応すべき領域が残されています。
2 「物のパブリシティ」と「顧客吸引力」概念の峻別
原審が導入した「物のパブリシティ権」概念は、もともと顧客吸引力(commercial value)という経済的事実に着目したものであり、必ずしも「権利」概念に立脚する必要はありません。
すなわち、競走馬の馬名や外観に経済的価値があるとしても、それは財産的利益の客体にすぎず、直ちに排他的支配の対象となるわけではないという最高裁の整理は、理論的に明快です。
このように、「経済的価値の存在」と「法的権利としての保護」は区別されるべきであり、最高裁は両者を峻別したうえで、後者を否定した点に意義があります。
3 「人」と「物」の線引き
本判決は、パブリシティ権の射程を「人」に限定する方向性を明確にしたものと評価できます。
後のピンク・レディー事件(最三小判平成24年2月2日)は、「人の氏名・肖像の利用」は人格権に基づくものであり、これを経済的側面で保護することは人格権の延長として可能としました。
これにより、
-
「人」については人格的利益の経済的側面としての保護
-
「物」については、既存の知的財産法に基づく保護
という二層構造が確立されたといえます。
この区別は、現代のAI生成物やメタバース上のデジタルアセットの扱いを考える上でも示唆的です。
「人格」や「創作性」を有しない対象にまで排他的権利を及ぼすことは、現行法体系の整合性を損なうおそれがあります。
4 実務的影響
本判決は、ゲーム・映像・広告等における実在物の名称・外観の利用自由の範囲を明確化した意義を持ちます。
企業が、実在の競走馬・車両・建築物・ブランド製品などを登場させる際、これらの「物」に固有のパブリシティ権を懸念して利用を控える必要は基本的にないとされます。
もっとも、表示方法が他人の商品表示や商標と混同を生じさせる場合には、不正競争防止法上の責任が生じ得るため、利用態様の誤認・混同防止措置(表示の明確化、クレジット表記等)が重要です。
5 学説上の位置づけと今後の課題
本判決は、学説上も一般に「物のパブリシティ権の否定判例」として定着しています。
もっとも、経済的価値を持つ「物」や「キャラクター」について、権利保護の必要性が全くないわけではありません。
実務的には、
-
商標法・意匠法による登録保護
-
不正競争防止法による商品等表示保護
-
契約・ライセンスによる私法的管理
によって補完的に対応すべき領域と位置づけられています。
したがって、本判決は、権利の法源を明確に限定しつつも、既存法体系による柔軟な利益調整を促す方向性を示したものと総括できます。
6 総括
以上より、本件最高裁判決は、
-
知的財産権の法定主義を再確認し、
-
「物」にまでパブリシティ権を拡張する下級審の判断を明確に排した点で、日本の判例法上きわめて重要な転換点となりました。
本判決は、権利保護の限界を明確にする一方で、顧客吸引力の公正な利用秩序を確立するという課題を残しており、今後の立法的・学理的検討の出発点と位置づけることができます。