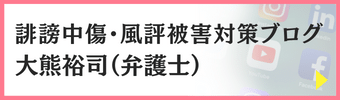はじめにーなぜ「損害額算定」が最大の争点になるのか
著作権侵害が問題となるとき、最終的に当事者の利害を大きく左右するのは
「侵害が成立するか」よりも、「いくらの損害賠償になるのか」という点です。
侵害の有無については、無断転載・無断配信・無断利用といった事実関係が比較的明確であれば、判断が分かれにくい場合も少なくありません。
しかし、損害額の算定となると事情は一変します。
民法709条の一般原則に従えば、損害賠償請求をする側(権利者)が、
・侵害がなければ得られたはずの利益
・侵害者が侵害行為によって得た利益
・それらと侵害行為との因果関係
を具体的に立証しなければなりません。
ところが、デジタルコンテンツの侵害では、アクセス数、広告収益、内部データなど、重要な情報の多くが侵害者側に偏在しています。
権利者が「正確な損害額」を証拠によって示すことは、実務上きわめて困難です。
このような事情を前提に設けられているのが、著作権法114条です。
114条は、損害額の立証を一定程度緩和し、代替的な算定方法を認めることで、権利者の救済を図るための特則です。
近年、この114条をめぐる実務は大きく動いています。
デジタル侵害への対応、特許法分野の損害論の影響、そして悪質事案に対する高額賠償の流れが重なり、従来の「低額にとどまりやすい」というイメージは大きく変わりつつあります。
以下では、114条各項の構造を丁寧に確認しながら、裁判例が示してきた実務の到達点を整理します。
第1章 著作権法114条1項ー逸失利益という考え方
1 114条1項の条文構造
114条1項は、権利者が本来得られたはずの利益(逸失利益)を、侵害数量等を基礎に算定するための規定です。令和5年改正により、条文上も「二段構造」が明確になっています。
著作権法114条1項(要約)
著作権者等が侵害者に対し損害賠償を請求する場合であって、侵害者が
① 侵害行為によって作成された物を譲渡し、又は
② 侵害行為を構成する公衆送信(送信可能化を含む)を行ったときは、
次の各号の合計額を損害額とすることができる。1号(数量×単位利益)
「譲渡等数量」のうち「販売等相応数量」を超えない部分(※「特定数量」があるときは控除後)× 権利者の「単位数量当たりの利益」2号(超過分等×ライセンス料相当)
譲渡等数量のうち販売等相応数量を超える部分、又は特定数量がある場合の当該数量×当該権利の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額
2 実務上の計算の基本(1号部分)
実務上の基本は、まず1号の枠組み、すなわち次の発想です。
・侵害によって供給された数量
×
・権利者の単位数量当たりの利益
ここでいう「利益」は、売上高そのものではなく、追加的に発生する費用(変動費)を控除した限界利益と理解されます。固定費や通常の広告費などは、原則として控除されません。
3 デジタル侵害と令和5年改正(受信複製の明確化)
従来、114条1項は「物の譲渡」を中心に構成されているとの理解が強く、ダウンロード配信やストリーミングのようなデジタル侵害への当てはめが論点となる場面がありました。
令和5年改正後の条文では、「譲渡等数量」の中に、侵害公衆送信を公衆が受信して作成した複製物(いわゆる受信複製物)が含まれることが明確にされました。
これにより、海賊版サイトのダウンロード回数や、無断配布の件数等を基礎に、114条1項を用いて損害算定を組み立てる道筋が整理されています。
4 「覆滅(特定数量)」と減額の問題
もっとも、114条1項(特に1号)を用いた算定が常にそのまま通るわけではありません。実務で頻繁に問題となるのが、次の点です。
「侵害がなければ、その数量分が本当に売れたのか」
たとえば、
・侵害品が無料で提供されていた
・極めて安価で配布されていた
・正規版とは異なる利用層に向けられていた
といった事情がある場合、「侵害数量=正規販売数量」とは評価しにくくなります。
BL同人誌海賊版サイト事件(東京地判令和2年2月14日・裁判所ウェブサイト)では、ダウンロード回数を基礎に損害額を算定する枠組みが検討されつつも、無料閲覧等の事情を踏まえて大きな調整(減額)が行われています。
この種の裁判例は、114条1項が万能ではなく、市場性や利用態様に応じて修正され得る規定であることを示しています。
第2章 著作権法114条2項ー侵害者の利益という視点
1 114条2項の条文
114条2項は、侵害者が侵害行為によって得た利益を、権利者の損害と推定する規定です。
著作権法114条2項(要約)
著作権者等が侵害者に対し損害賠償を請求する場合において、侵害者が侵害行為により利益を受けているときは、その利益の額は、権利者が受けた損害の額と推定する。
ここでいう「利益」も、売上高そのものではなく、原価等を控除した限界利益と解されています。
侵害者側に明確な収益構造(販売利益、広告収益など)がある場合には、有力な算定手段となります。
2 因果関係と調整の問題
もっとも、114条2項も機械的に適用されるわけではありません。
実務では、
・侵害行為と利益との因果関係
・他の要因による利益との切り分け
が問題となり、侵害者の利益全額がそのまま損害と認定されるとは限りません。
この点については、特許法分野の裁判例が大きな示唆を与えています。
第3章 特許法判例の影響と「項の併用」という発想
近年の著作権実務に強い影響を与えているのが、特許法102条をめぐる損害賠償判例です。
特に、美容器事件(知財高大判令和2年2月28日・裁判所ウェブサイト)と椅子式マッサージ機事件(知財高大判令和4年10月20日・裁判所ウェブサイト)では、概略、次の発想が示されました。
・侵害部分が製品全体の一部であることを理由に当然に大幅減額するのではなく
・減額された(切り捨てられた)部分を、ライセンス料相当額で評価し得る場面がある
この考え方は、著作権分野にも応用可能です。
たとえば、
・ゲームソフト全体の中で、無断使用された音楽は一部にすぎない
・映像作品の一部しか利用されていない
といった場面で、「一部だからほとんどゼロ」という結論に直行せず、別の算定軸(使用料相当額)で評価するという発想が、理論的に整理されつつあります。
第4章 著作権法114条3項ー使用料相当額と高額化
1 114条3項の条文
114条3項は、逸失利益や侵害者利益の立証が難しい場合に用いられる、いわば「使用料相当額」のルートです。
著作権法114条3項(要約)
著作権者等は、侵害者に対し、当該権利の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を、自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
この規定は、長らく「最低限の救済」にとどまると考えられてきました。
2 ファスト映画事件と評価の転換
しかし、映画を無断で短縮・編集して公開したファスト映画事件(東京地判令和4年11月17日・裁判所ウェブサイト)では、裁判所は約5億円という極めて高額な損害賠償を認めました。
裁判所は、
・1回再生あたりの価値
・再生回数
を基礎に、使用料相当額を積み上げる方法を採用しました。
これは、形式的には114条3項を用いながら、
実質的には通常のライセンス料を大きく超える評価を行ったものと理解できます。
3 著作権法114条の5
令和5年改正により、裁判所が損害額を定める際の裁量を示す規定として、114条の5が整理されました。
著作権法114条の5(要約)
侵害により損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
つまり、114条の5は、「損害額の立証が性質上極めて困難」という場面で、裁判所が証拠関係を踏まえて相当額を認定できる、という立証困難の救済(裁量認定)の根拠です。
おわりにー著作権法114条の現在地
著作権法114条は、単なる計算規定ではありません。コンテンツの価値を金銭的に評価し直し、実効的救済につなげるための制度です。
現在の実務を整理すると、重要なポイントは次の3点に集約されます。
・デジタル侵害への本格対応(1項の射程整理等)
・各項を組み合わせて評価する発想(主張構成の工夫)
・悪質侵害に対する高額化の進展(3項の積上げ等)
著作権侵害は、もはや「軽いリスク」ではありません。侵害を発見した場合、削除要請だけで終わらせるのではなく、114条を前提とした損害賠償請求を検討することが、これからの標準的な対応になっていくでしょう。