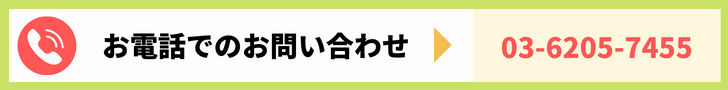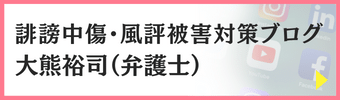【詳細解説】聖教新聞「最凶タッグ事件」ーなぜ新聞写真の無断ツイートは”適法”と判断されたのか?
「このニュース、一言もの申したい!」 SNSで記事を引用し、意見を投稿する。今や日常的な光景ですが、その行為が「著作権侵害」にあたるか否かの境界線は、実は非常に曖昧です。
今回ご紹介するのは、その境界線に重要な指針を示した「聖教新聞写真事件」、通称「最凶タッグ事件」について、裁判所がどのような理屈で判断を下したのか、判決文の内容に踏み込みながら、より詳しく、そして分かりやすく解説します。
この事件は、令和6年9月26日に東京地方裁判所(原審)・裁判所ウェブサイト、そして令和7年7月31日に知的財産高等裁判所(控訴審)・裁判所ウェブサイト で判決が言い渡され、いずれも被告(会員)の投稿を「適法」と判断しました。その背景には、Twitterというメディアの特性や、現代社会における「批評」のあり方を深く洞察した、画期的な判断がありました。
事件の概要:何が、どのように争われたのか?
まず、事件の背景を正確に把握しましょう。
-
訴えた側(原告): 宗教法人 創価学会
-
訴えられた側(被告): 創価学会の会員である個人
【争点となった行為】 被告は、平成30年10月から令和元年10月までの約1年間、自身が購読する聖教新聞の紙面をスマートフォンで撮影し、そこに掲載された写真と共に、原告の活動などに対する批評文を付けて、25回にわたりTwitterに投稿しました。
その一連の投稿のきっかけとなった最初のツイートの本文が、原告幹部2名が写った写真に添えられた「最凶タッグ」という5文字でした。
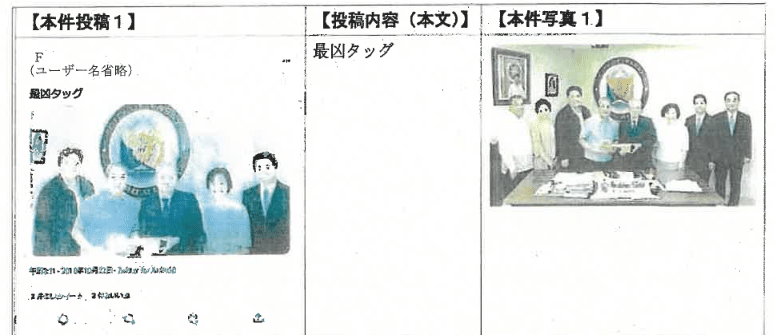
これに対し、創価学会は「聖教新聞に掲載された写真の著作権(送信可能化権)を侵害された」と主張。被告の行為は不法行為にあたるとして、約419万円の損害賠償を求めました。
裁判の核心:著作権法の「壁」をどう乗り越えたか?
この裁判の最大の争点は、被告の投稿が著作権法で例外的に認められている「引用」(著作権法32条1項)などのルールに当てはまるか否かでした。
「引用」が認められるには、法律で定められた複数の条件をクリアする必要があります。被告の行為は、この条件を一つ一つ満たしていると裁判所は判断しました。その詳細なロジックを見ていきましょう。
裁判所はなぜ「適法」と判断したのか?
控訴審である知的財産高等裁判所は、極めて論理的に被告の行為の適法性を認めました。その判断を支えた、特に重要な3つのポイントを深掘りします。
ポイント1:【主従関係】「Twitter(X)の常識」を司法が認定!量的比較だけで決まるものではなく、目的や態様を踏まえ社会通念で判断される
「引用」では、自分の意見が「主」、引用部分が「従」という主従関係が必要です。
原告は「投稿本文は短く、写真が大きく表示されており、写真が『主』になっている」と主張しました。しかし、裁判所はこの主張を、Twitter(X)というメディアの特性を理由に退けます。
「ツイッターにおいては、本文で投稿することができる文字数に制限があるから、ツイッター上で他の著作物を引用して表現活動を行う場合には、外見上、引用部分よりも本文の方が短くなることは通常よくみられることである。この場合に単純に引用部分と本文との長短や量を比較し、主従関係を判断することは、ツイッターを利用して「つぶやく」という形で行われる表現活動を不当に制限する効果をもたらすおそれがある。」
これは画期的な判断です。裁判所は、プラットフォームの仕様という「SNSの常識」を判断基準に取り入れました。そして、投稿の目的や内容といった実質的な面から見れば、被告の批評こそが「主」であり、写真はそれを補足する「従」に過ぎないと認定したのです。
ポイント2:【引用の目的】写真そのものではなく「報じられた出来事」の批評でもOK
ここが本判決の核心部分です。報道写真の引用は、写真の撮り方などを批評する場合にしか許されないのでしょうか?裁判所は、より広い範囲を認めました。
「本件各写真(引用)それ自体を批評する場合に限らず、本件各写真(引用)とまた、著作権法32条1項の規定の文言上、引用の必然性や厳格な必要性までは要求されていないから、著作権の保護と利用の調和という観点からは、本件各写真(引用)それ自体を批評する場合に限らず、本件各写真(引用)と一体となった記事により報道された出来事と引用の目的とに関連性が認められる場合には、商業的利用の有無、前記主従関係の要件の充足その他の事情を考慮した上で、「引用の目的上正当な範囲内」の引用であると認めることは妨げられない。」
つまり、「この写真は構図が…」と写真自体を批評しなくても、「この写真に写っている〇〇というイベントの進め方はどうなのか?」と、ニュースの中身を批評するために写真を使うことも、正当な引用の目的だ、と明確に示したのです。
裁判所は、報道機関が記事や写真を公にするのは「広く知らしめ、読者による意見等の形成に資することを目的として」いると指摘。その目的に沿って読者が批評を行う際に、出来事を視覚的に伝える報道写真を利用することは、表現活動の自由を保護する必要性が高い、と考えたのです。
ポイント3:【公正な慣行】厳密な出所表示がなくても文脈で判断
「引用」には、出所の表示など「公正な慣行」に従うことも求められます。被告の投稿には、毎回必ずしも「聖教新聞より」と明記されていませんでした。
しかし、裁判所はこれも問題ないと判断します。その理由は、以下の3点です。
-
被告は継続的に同様の体裁(新聞の撮影写真+批評)で投稿していたこと。
-
投稿内容や被告の立場から、主な読者は原告の会員など事情をよく知る人々であり、文脈から出所が聖教新聞であることは容易に推測できたこと。
-
そもそも、原告の関係者と思われる他のアカウントも、聖教新聞の記事を出所表示なく投稿している例が多数あったこと。
これらの事情を総合的に考慮し、社会通念上、許される方法だったと認定しました。
法改正は過去に遡る?「写り込み」のルール
この裁判には、もう一つ非常に興味深い法律論争がありました。それは、意図せず「写り込ん」でしまった写真の扱いです。
被告の投稿には、批評対象の記事の隣にあった、全く関係のない写真まで写ってしまったものがありました。この「写り込み」にも著作権法のルール(付随対象著作物の利用、30条の2)があります。
実は、このルールは被告が投稿した後に、より使いやすいように条件が緩い新ルールに法改正されていました。
ここで、「過去の行為なのだから、厳しかった古いルールで裁くべきだ」と原告は主張しました。しかし、裁判所はこれを退け、新しい、緩やかなルールを適用すると判断したのです。
その理由は、「この法改正は、厳しすぎた要件を緩和し、国民の権利を広げるために行われたもの。国民に有利な改正について、過去の行為への適用を認めないと不当な結果になる」というものでした。これは、法解釈として非常に重要で、今後の裁判にも影響を与える可能性のある判断です。
そして、その新しいルールに基づき、写り込み部分の面積が小さいことなどから、この点も適法だと認められました。
結論:この判決が社会に与えるインパクトと私たちが学ぶべきこと
この「最凶タッグ事件」判決は、単なる一つの著作権裁判ではありません。SNSが主要な言論空間となった現代社会において、表現の自由と著作権保護のバランスをどう取るべきか、司法が示した具体的で新しい答えです。
私たちがこの判決から学ぶべき、より深い教訓は以下の通りです。
-
司法はデジタル社会の現実を見ている
裁判所はもはや、旧来の常識だけで判断していません。Twitterの文字数制限のようなプラットフォームの特性を理解し、現実に即した柔軟な解釈を行う姿勢を明確にしました。 -
批評のための利用は、より広く保護される傾向にある
商業目的での無断利用は依然として厳しいですが、公共性のある事柄に対する「批評」という表現活動のためであれば、著作物の利用は比較的広く許容される方向性が示されました。 -
形式より実質。目的と態様が重要
「出所表示がない」「写真が大きい」といった形式的な部分だけでなく、「何のために(目的)」「どのような方法で(態様)」利用したのか、という実質がより重要視されます。不鮮明なスマホ撮りであったことも、「鑑賞や再利用が目的ではない」という被告の主張を補強しました。
もちろん、この判決が出たからといって、どんな写真でも自由に投稿していいわけではありません。しかし、正当な目的意識と、著作権者への配慮(出所表示の徹底など)を持ってSNSを利用する限り、あなたの表現活動は法律によってしっかりと守られる可能性が高いのです。
この画期的な判決を参考に、萎縮することなく、しかし責任を持って、インターネットでの言論活動に参加していくことが、私たち一人ひとりに求められています。