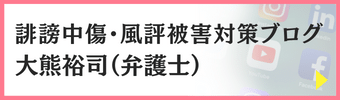著作権の利用の「譲渡」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
著作権の譲渡と許諾の区別
自分が作成した著作物を第三者に利用させる形式としては、①著作権を譲渡する方法、②著作権の利用許諾をする方法があります。なお、著作権は、支分権の束で成り立っていますので、必ずしもすべての支分権を譲渡したり、利用許諾をする必要はありません。例えば、作家が出版社と書籍の出版に関して契約をするときに、電子書籍の販売は自分で行いたいということであれば、インターネット販売に必要な権利(公衆送信権)については、譲渡や許諾の対象から外しておけばよいのです。
契約書を作成していても、紛争になったケース
著作権者と第三者との契約内容が、著作権の譲渡なのか、著作権の利用許諾なのかについては、契約書が作成されている場合には問題にならないとも思えます。
しかし、被告から注文を受けてウェブサイトを作成した原告が、被告が無断でウェブサイトを複製して、新たなウェブサイトを作成してインターネット上で公開したことに対して、差止や損害賠償等を求めた裁判で、ライブ株式スクール事件(大阪地判令和元年10月3日・裁判所ウェブサイト)は、「注文書の「仕様」欄に,「全面リニューアル後の成果物の著作権その他の権利は,制作者のP1に帰属するものとする。」と記載がある」という記載があるものの、ウェブサイトの著作権が原告に帰属するとの合意が成立したと認めることはできないとし、著作権は被告に譲渡されたと認定しました。
本件制作業務委託契約については,被告ピー・エム・エー名義で作成された本件注文書の「仕様」欄に,「全面リニューアル後の成果物の著作権その他の権利は,制作者のP1に帰属するものとする。」と記載がある。
しかしながら,被告P3本人の尋問の結果によっても,被告ピー・エム・エーが,原告と上記記載に係る合意を成立させる趣旨で,本件注文書に上記記載をしたとは認められないし,他に,原告と被告ピー・エム・エーとの間で上記記載に係る合意が成立したと認めるに足りる証拠は提出されていない。
原告ウェブサイトの制作の対価を324万円と定める本件制作業務委託契約において,制作後の原告ウェブサイトの権利が原告に帰属するとすることが不合理であることは前記⑵で述べたとおりであり,あえてそのように合意するとすれば,その合意は明確なものでなければならず,本件においてそのような合意が成立したと明確に認めるに足りる証拠がないことは上記ア及びイのとおりであるから,被告ピー・エム・エーと原告の合意によって,原告ウェブサイトの著作権が原告に帰属したと認めることはできない。
これとは逆に、控訴審である知財高判令和2年10 月28日・裁判所ウェブサイトは、原告(控訴人)から被告(被控訴人)への譲渡の成立を否定しました。
被控訴人らは,①被控訴人ピー・エム・エーは,控訴人に対し,324万円という高額な原告制作ウェブサイトの制作対価を支払っていること,②原告制作ウェブサイトは,専ら被控訴人ピー・エム・エーが使用するためにその委託によって制作されたものであり,控訴人が原告制作ウェブサイトに係る著作権を保有する必要性及び合理的理由がないこと,③被控訴人ピー・エム・エーは,自身の企業活動に合わせて,原告制作ウェブサイトの内容を変更したり,保守委託先を変更したり,格納サーバを変更したりすることが当然に予定されているにもかかわらず,被控訴人ピー・エム・エーが原告制作ウェブサイトに係る著作物の著作権を有しないとすれば,その都度,控訴人の許諾を得なければ,これらを実現できず,企業活動が著しく阻害されること,④原告制作ウェブサイトを制作した控訴人が自ら原告制作ウェブサイトに「CopyrightⒸライズ株式スクール All Rights Reserved」と表示していることからすると,原告制作ウェブサイトに係る著作物の一部として本件画像著作物の著作権は,控訴人から被控訴人ピー・エム・エーへ黙示に譲渡された旨主張する。
しかしながら,前記認定事実によれば,控訴人と被控訴人ピー・エム・エーは,平成28年1月6日付け本件保守契約書(甲146)をもって締結した本件保守業務委託契約に基づいて,同年4月22日付け本件注文書(甲13)をもって,被控訴人ピー・エム・エーが控訴人に対し,旧ウェブサイトを全面的にリニューアルしたウェブサイトの制作を代金324万円で発注する旨の本件制作業務委託契約を締結し,控訴人は,本件制作業務委託契約に基づき,原告制作ウェブサイトを制作したものであるところ,本件保守契約書には,「本件成果物の著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む)その他の権利は,制作者に帰属するものとする。」(14条3項)との規定があること,本件注文書の「備考」欄には,「全面リニューアル後の成果物の著作権その他の権利は,制作者のBに帰属するものとする。」との記載があることに照らすと,控訴人と被控訴人ピー・エム・エーは,控訴人が制作した原告制作ウェブサイトに係る著作物の著作権は控訴人に帰属することを確認しており,控訴人において上記著作権を被控訴人ピー・エム・エーに譲渡する意思が有していたものとは到底認めることはできない。
また,控訴人が原告制作ウェブサイトの制作前に著作した本件画像著作物の著作権を被控訴人ピー・エム・エーに譲渡すべき合理的事情はない。
ライブ株式スクール事件でも分かるように、契約書(書面)があったとしても、その記載されている表現が明確でない場合は、著作権の譲渡があったとは確実に認められるわけではなく、裁判所の判断に委ねられることになりますので、契約書の作成には注意が必要でしょう。
契約書がない場合
契約書がないまま、自分の著作物を第三者に利用させるような場合に、それが著作権の譲渡なのか、著作権の利用許諾なのかが争われる場合、なお更その判断は困難になります。しかし、世の中でトラブルになり、裁判に発展しているのは、契約書がない事案が多いのです。
契約書が作成されていないと聞くと、当事者がいい加減だったのではないかという印象を抱きますが、著作権の世界では、大企業が当事者であったとしても、契約書が作成されないことや、契約書が作成されたとしても、著作権の帰属については触れていないことは珍しいことではありません。
その理由は明らかではありませんが、著作権のことまで気が回らなかったり、当事者の力関係から、著作権の帰属については明確にしにくいなどの理由が考えられます。著作権を譲渡してしまえば、自分が制作した著作物に関しては、著作権を主張できなくなってしまうのですから、契約書で白黒はっきりとはさせたくないのが当事者の気持ちかもしれません。
対価の支払額を検討した裁判例
大阪地判平成19年7月26日・裁判所ウェブサイトは、プログラムの著作権の譲渡契約があったか否かの判断において、注文者が受託者(製作者)に支払った報酬額によって、譲渡契約まで含まれていたか否かを判断しています。
プログラムの著作権を譲渡する場合,当然のことながら,譲渡後は,譲渡人は同プログラムの著作権(著作者人格権を除く)に関して何らの権利も有さなくなるのであって,同著作権に係る著作物を自らも複製・頒布・翻案することができない上,第三者が同著作物を複製等しても,同著作権に基づく差止請求,損害賠償請求をすることもできなくなる。他方,譲受人は,同著作物を複製・頒布・翻案することができるし,第三者(譲渡人も含む)による同著作物の複製等に対して,同著作権に基づく差止請求や損害賠償請求をすることができる。
このように,著作権を譲渡するということは,著作権法21条ないし28条が規定する著作者の権利を全て譲渡するということであり,対象となる著作物の経済的価値が大きければ大きいほど,譲渡する著作権の対価も高額なものとなるのは当然である。そして,著作物の経済的価値の大小については,同著作物の複製物が販売されている場合は,その販売価格の多寡が参考となる。
本件において,G1X MS-DOS版の著作権の譲渡の対価であると評価することができる程度の額の金銭の授受の有無について検討すると,GDX等の開発からG1Xシリーズの開発ないし修正に至るまで,例えば,GDX等の複製物が少なくとも一船分200万円ないし300万円で販売されていることに見合うような著作権譲渡の対価が,著作権の譲渡時に授受されたと認めるに足りる証拠はない。
むしろ,G1X MS-DOS版については,GDX等の複製物が一船分200万円ないし300万円で販売されるものについて,Aは,システムを導入する作業船に併せてプログラムを修正し,複製物が作業船所有者に納品,販売される際に,一船につき70万円ないし90万円等の報酬を受領していたというものであった。このことからすると,G1X MS-DOS版に関してAに支払われた対価は,著作権の譲渡代金ではなかったと思われる。
もっとも、著作権の譲渡まで含んだ報酬額か否かは、必ずしも明確な線引きはできませんので、報酬額によって判断ができる事例ばかりではないと思われます。
出版契約における「買取り」の慣行
著作者と出版社との間で契約書がない場合、出版社としては、原稿・原画は出版社の買取りとなり、その版権(再版権)は当該出版社に帰属するものとして取り扱われる慣行があると主張する場合があります。
この点について争われた裁判例として、東京地判平成24年3月29日・裁判所ウェブサイトがあります。被告(出版社)による、絵本の原画は出版社の買取りとなり、その版権(再版権)は当該出版社に帰属するものとして取り扱われる慣行があるとの主張は排斥されています。
被告は,さらに,一般的に絵本の原画は出版社の買取りとなり,その版権(再版権)は当該出版社に帰属するものとして取り扱われる慣行があると主張し,被告代表者の供述及び登龍館の元従業員であるHの陳述書(乙7)中には,これに沿う部分がある。
しかしながら,被告代表者の上記供述等については,これを裏付けるに足りる客観的な証拠はなく,かえって,証拠(甲45)及び弁論の全趣旨によれば,他の出版社の制作した絵本の中には,原画の著作権が画家(著作者)に帰属するものとして取り扱われているものが少なからず存在することがうかがえる。したがって,被告代表者等の上記供述を採用することはできない。
判断が分かれた裁判例
職業写真家である原告が、出版社である被告に対し、本件写真の著作権が原告に帰属するのに、被告は、原告の承諾なく、本件書籍に本件写真を掲載し、原告の著作権(複製権、公衆送信権)等を侵害したなどと主張して、損害賠償等を求めた事案で、東京地判平成25年 7月19日・裁判所ウェブサイトは、以下のとおり述べ、著作権の譲渡が合意されたとはいえないとしました。
ア 補助参加人は,原告に対し,撮影された写真の著作権が全て補助参加人に帰属することを十分に説明し,原告はこれを了承していた旨主張し,これに沿うD及びEの陳述書(丙25,27)及び証人尋問における供述がある。
そこで検討するに,D(補助参加人代表者)は,証人尋問において,撮影者の採用面談の際に,撮影に関する権利は全て「買取り」であることを説明しているし,原告の採用面談では,撮影した写真が「買取り」であることを説明した旨供述する。また,Eは,証人尋問において,補助参加人に勤務していた際には,カメラマンと初めて仕事をするときに写真に関する権利は全て補助参加人のものになる旨説明しており,原告と初めて仕事をしたときにも同じ説明をした旨供述する。
しかしながら,Dの供述では,原告に対する説明は撮影した写真の「買取り」にとどまり,具体的に著作権の譲渡について説明したものではない。このような「買取り」には,著作権の譲渡の意味で使用する場合のほか,一定範囲での利用許諾料の支払が定額である意味で使用する場合等があると解されるから,たとえDが原告に対して「買取り」と説明していたとしても,それが直ちに著作権の譲渡の意味であったことにはならない。また,Eの供述も,写真に関する権利は全て補助参加人のものになる旨の説明にとどまる上,その説明には「著作権」という言葉を使用していない旨も供述するから,著作権の譲渡について説明したものとはいい難い。
また,証拠(甲12)及び弁論の全趣旨によれば,補助参加人は,原告に対し,原告撮影の写真について,その複製物を第三者に交付することの承諾を求めていることが認められるから,補助参加人は,原告撮影の写真について,その著作権が原告に帰属することを前提として行動していることがうかがえる。
以上に加え,原告は,陳述書(甲14)及び本人尋問において,写真の「買取り」や著作権の扱いについて説明がなかった旨を供述していることや,補助参加人が撮影者との間で著作権の譲渡について契約書を作成することが困難であった事情が見当たらないことに照らすと,原告と補助参加人との間で,原告撮影の写真について,著作権の譲渡の合意があったとは認められないし,その他これを認めるに足りる証拠もない。
これに対して、控訴審である知財高判平成25年12月25日・裁判所ウェブサイトは、包括的な合意の存在を認定し、口頭による合意であり、書面による明確な合意ではないことなどの事情を総合的に考慮して、著作権の譲渡は否定したものの、包括的許諾がなされたと認定しました。
ウ 以上によれば,第1審原告は,平成16年頃から平成22年7月中旬頃までの間は,補助参加人との間で,補助参加人の依頼により撮影した写真に関する権利は全て補助参加人に譲渡するとの,いわゆる買取りの合意の下に,補助参加人から依頼されて多数の写真を撮影してその収入を得ていたものと認められ,このような包括的な合意があったことは,第1審原告が,撮影した写真フィルムについても,補助参加人に渡したままその利用を委ねていたことや,その後,多数回にわたり,その写真が二次利用され,別の書籍等が出版されることになっても,第1審原告が,事前の承諾を求めることもなく,二次利用の利用料の支払もなく,かつ当該書籍が出版されていることを知っていたものと推認される立場にありながらも,上記期間内は何らの苦情を述べてきていないとの事実とも符合するものである。もっとも,この包括的合意の趣旨が,写真の著作権の補助参加人への譲渡であるか,それとも将来の補助参加人ないし他社による書籍出版その他における二次利用も含めた包括的許諾であり,その対価については,当初の撮影時の支払によるものとするとの合意であるかについては,これが口頭による合意であり,書面による明確な合意ではないこと,及び,そのためか,補助参加人においても過去において前記イ(ウ)及び(エ)のようなやや不明瞭な対応をしたこともあったことなどの事情を総合的に考慮すれば,上記包括的合意の趣旨は,著作権の譲渡ではなく,上記のような包括的許諾の趣旨であったものと認めるのが相当である。そうすると,上記期間内に撮影された本件写真の著作権についても,上記包括的合意に基づき,第1審原告から補助参加人に対し,その二次利用も含め,包括的許諾がなされたものと認められる。
契約書がない場合における譲渡か許諾かの判断は微妙
上記裁判例からも分かるように、著作権の譲渡か利用許諾かを契約書に明記していない紛争が訴訟に発展した場合、その判断は裁判所でも別れ得るのであり、判決が出ないと分からない(一審判決が出ても控訴審では分からない)ということになりかねません。
最終的に裁判所判断になる事態が生じたときは仕方がありませんが、事前にそのような事態が生じないような契約書による手当てが重要だと思われます。