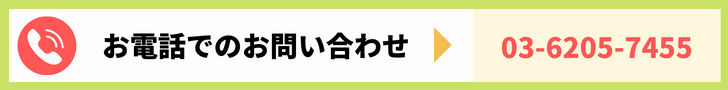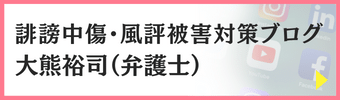マイホームのデザインには、作り手の想いや個性が詰まっています。しかし、そのデザインが法的にどこまで「著作物」として保護されるのか、ご存知でしょうか?今回は、住宅デザインの著作権が争われた注目の裁判例「積水ハウス事件」について、第一審判決(大阪地裁 平成15年10月30日判決・判例タイムズ1146号267頁)、控訴審判決(大阪高裁 平成16年9月29日判決・裁判所ウェブサイト)について、専門的な内容を分かりやすく解説します。住宅業界の方も、デザインに関わる方も、そしてこれから家を建てる方も、ぜひご一読ください。
発端:「グルニエ・ダインJX」をめぐる争い
この事件は、大手ハウスメーカーである積水ハウス株式会社(以下、原告)が、株式会社サンワホーム(以下、被告)に対し、自社製品のデザイン模倣などを訴えたものです。
主な争点
事件は大きく二つの柱で構成されていました。
-
第1事件:住宅デザインの保護
(1) 著作権侵害: 原告は、自社が企画開発した高級注文住宅「グルニエ・ダイン」シリーズの一つである「グルニエ・ダインJX」(以下、原告建物)は、その独創的な外観デザインから「建築の著作物」(著作権法10条1項5号)に該当すると主張。被告が住宅展示場で建築した注文住宅(以下、被告建物)は、原告建物を複製または翻案したものであり、著作権を侵害していると訴えました。
(2) 商品等表示としての保護(不正競争防止法): 被告建物は、原告建物の商品形態を模倣したものであり、不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣)に違反するとも主張しました。
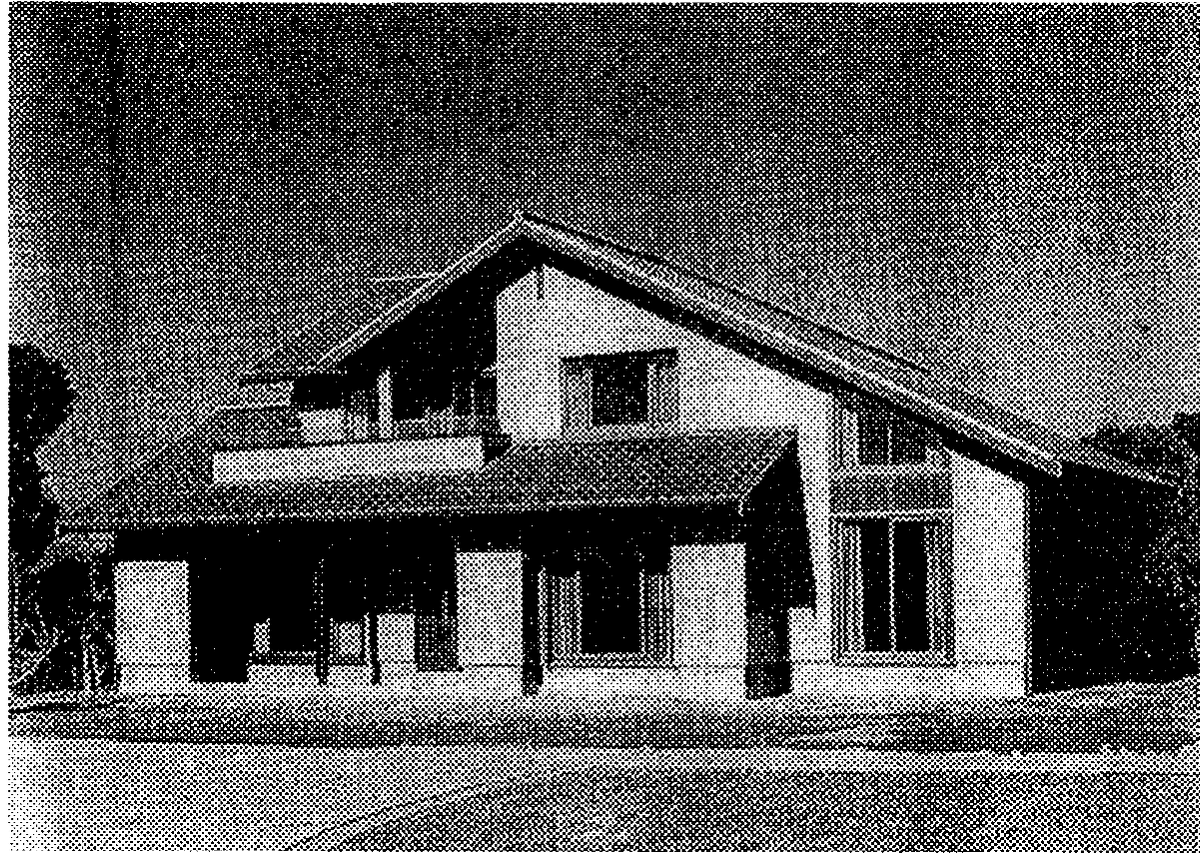

-
第2事件:住宅写真の保護
(1) 原告は、原告建物とは別の自社建物を撮影し、コンピュータグラフィックス(CG)処理を施した写真(以下、原告写真)をカタログに掲載していました。これに対し、被告がこの原告写真をさらにCG処理した写真(以下、被告写真)を自社の住宅展示場の広告等に使用した行為が、原告写真の著作権を侵害する(複製または翻案)と主張しました。
原告はこれらの主張に基づき、被告建物の建築・販売等の差止め、パンフレットや被告写真等の廃棄、そして損害賠償を求めました。
第一審(大阪地裁)の判断:「建築の著作物」の壁は厚い
平成15年10月30日、大阪地方裁判所は以下の判断を下しました。
-
建築の著作物性(争点①):否定
(1) 裁判所はまず、著作権法により「建築の著作物」として保護される建築物は、同法2条1項1号の定める著作物の定義に照らし、美的な表現における創作性を有するものである必要があると確認しました。
(2) その上で、一般住宅について重要な判断基準を示します。一般住宅であっても実用性や機能性のみならず、美的要素も加味されて設計・建築されるのが通常であるとしつつ、この事実だけをもって直ちに「建築の著作物」性を肯定し著作権法上の保護を与えることは、「同法2条1項1号の規定に照らし広きに失し,社会一般における住宅建築の実情にもそぐわない」と指摘しました。この背景には、建築が本来的に実用性を重視するものであり、安易に著作物性を認めると後続の建築活動を不当に制約しかねないという懸念があります。また、意匠法が工業デザインを保護する役割を担っていることとの関係も考慮されたと考えられます。
(3) そして、一般住宅が「建築の著作物」と評価されるためには、「一般人をして、一般住宅において通常加味される程度の美的要素を超えて、建築家・設計者の思想又は感情といった文化的精神性を感得せしめるような芸術性ないし美術性を備えた場合、すなわち、いわゆる建築芸術といい得るような創作性を備えた場合であると解するのが相当である」という、非常に高いハードルを示しました。この点について、判例タイムズの解説では、この基準が一般住宅の著作物性に関する従来の学説(例えば、文部省著作権制度審議会昭和41年答申説明書など、社会通念上美術の範囲に属する場合に著作物性を肯定する考え方)と軌を一にするものであると指摘されています。しかし、「どのような場合に、社会通念上美術の範囲に属するものとして『建築の著作物性』が肯定されるのかは、必ずしも明らかではない」という課題も依然として残ります。この「建築芸術」という基準は、単に美しい、あるいは個性的であるというだけでは足りず、美術作品としての鑑賞に堪えうるほどの高度な芸術性が求められることを意味します。
(4) 原告建物については、確かに美的な面での創作性や知的活動の成果が認められるものの、それらは「一般住宅を建築する上で通常行われている程度にとどまるもの」であり、「一般人をして建築家・設計者の思想又は感情といった文化的精神性を感得させ、美術性や芸術性を認識させるに至っていない」として、著作物性を否定しました。具体的には、原告建物が有する片流れ大屋根、インナーバルコニー、勾配破風サッシといったデザイン要素やその組み合わせは、試行錯誤の成果ではあるものの、従来の住宅建築に見られる要素の延長線上にあると評価され、「建築芸術」の域には達していないと判断されました。近時の注文住宅(モデルハウス)が様々に趣向を凝らし、外見上の美しさを重視しているものが多い中で、本判決は今後の実務の参考になると解説文は評価しています。
(5) 原告が主張したグッドデザイン賞の受賞についても、受賞理由が機能面なども含む総合的な評価であり、直ちに建築芸術としての美術性・芸術性を裏付けるものではないと判断されました。 -
商品形態の模倣(不正競争防止法、争点②):否定
(1) 裁判所は、建物の玄関部分のみを「商品の形態」とすることはできないとしました。
(2) その上で、原告建物と被告建物を比較検討した結果、玄関部分のみを比較しても相違点が多く、建物全体として見ても多くの相違点が存在するため、形態模倣にはあたらないと判断しました。 -
写真の著作物性(争点③):肯定
原告写真については、「被写体の選定,撮影の構図,配置,光線の照射方法,撮影後の処理等の処理において創作性があるものと認められ,思想又は感情を創作的に表現したものとして,著作物性を有する」と認定しました。判例タイムズの解説では、この判断は、平面的な作品を忠実に再現することを目的とした写真の著作物性を否定した裁判例(東京地判平10.11.30)や、野生イルカの写真のように撮影意図に応じた構図決定やシャッターチャンスの捉え方に創作性を認めた裁判例(東京地判平11.3.26)と同旨の見解に立つものとして紹介されています。これは、建物そのものが著作物でなくても、それを表現した写真には撮影者の創作性が発揮され得ることを示しています。 -
写真の複製・翻案(争点④):肯定
被告写真は原告写真に依拠して原告写真を複製したものであると認め、著作権侵害にあたると判断しました。
この結果、第一審では、原告の請求のうち、第2事件の写真に関する差止請求の全部と損害賠償請求の一部(40万円の支払い)のみが認容され、第1事件の建築の著作物性や不正競争防止法に基づく請求、及び第2事件のその余の損害賠償請求は棄却されました。
この第一審判決は、一般住宅の著作物性について具体的な判断基準を示し、そのハードルの高さを明確にした点で、実務上非常に参考になるものと言えます。
控訴審(大阪高裁)の判断:第一審支持、予備的請求も棄却
原告は第一審判決を不服として控訴。控訴審では、著作権侵害や不正競争行為に該当しない場合でも、被告の行為は原告の知的活動の成果にただ乗りする違法な模倣行為であるとして、民法709条(一般不法行為)に基づく損害賠償請求を予備的に追加しました。
しかし、平成16年9月29日、大阪高等裁判所は以下の通り判断し、原告の控訴を棄却、予備的請求も棄却しました。
-
建築の著作物性:第一審の判断を支持
(1) 控訴審は、第一審の「建築の著作物」に関する判断基準を基本的に踏襲しました。
(2) その上で、建築物は絵画や彫刻と異なり、美的鑑賞目的よりも実用目的で製作されるものであり、意匠法による保護対象でもない点を指摘。応用美術に類似した側面も有することから、著作権法で保護されるのは、「客観的、外形的に見て、それが一般住宅の建築において通常加味される程度の美的創作性を上回り、居住用建物としての実用性や機能性とは別に、独立して美的鑑賞の対象となり、建築家・設計者の思想又は感情といった文化的精神性を感得せしめるような造形芸術としての美術性を備えた場合」に限られると、改めて厳しい基準を示しました。この判断は、建築の著作物性を容易に認めると、実用的な建築物の自由な利用が妨げられ、かえって文化の発展に寄与するという著作権法の目的に反する結果になりかねないという考慮が働いているものと解されます。
(3) 原告建物は、この基準を満たさないと判断されました。 -
不正競争防止法による保護:第一審の判断を支持
商品形態の模倣についても、第一審と同様に、原告建物と被告建物の外観には相違があり、形態が同一ないし実質的に同一であるとはいえないと判断しました。 -
予備的請求(一般不法行為):棄却
被告建物が原告建物を模倣したとは認められない以上、被告の行為が違法な模倣行為として不法行為を構成することもないと判断しました。
この判例が示す「建築の著作物」保護の現実と深い考察
積水ハウス事件の第一審および控訴審判決は、住宅デザインの法的保護、特に著作権法における「建築の著作物」の解釈について、重要な示唆を与えています。
-
「建築の著作物」のハードルは極めて高い
本判決が一貫して示したのは、一般住宅が「建築の著作物」として著作権法上の保護を受けるためには、「建築芸術」と評価されるほどの高度な創作性・美術性が必要であるという点です。これは、単にデザイン性が優れている、あるいは市場で人気があるというだけでは不十分であり、実用的な機能とは別に、独立して美的鑑賞の対象となり得るレベル、すなわち、設計者の思想や感情が文化的精神性として感得されるレベルが求められることを意味します。 この高いハードルの背景には、いくつかの理由が考えられます。
(1) 建築活動の自由の確保
建築物は社会の景観を構成し、人々の生活空間となるものです。安易に著作権を認めると、類似のデザインの建築が困難になり、建築活動の自由が過度に制約される恐れがあります。
(2) 意匠法との役割分担
工業的に量産される物品のデザインは、主に意匠法によって保護されるべきという考え方があります。本判決当時は、建築物自体が意匠法の直接的な保護対象とは解されていませんでしたが(この点は後の法改正で変更されています。後述5参照)、著作権法で建築デザインを容易に保護することは、意匠法との役割分担やバランスを考慮すると慎重になるべきという考え方があったと推察されます。
(3) 著作権法の目的: 著作権法は文化の発展に寄与することを目的としています(著作権法1条)。実用性が主たる目的である一般住宅にまで安易に著作権保護を広げることは、必ずしもこの目的に合致しないという考え方もあり得ます。
判例タイムズの解説文でも触れられているように、従来の学説では「社会通念上美術の範囲に属する」場合に建築の著作物性を肯定する見解が示されてきましたが、本判決はこの「美術の範囲」を「建築芸術」のレベルにまで高めていると解釈できます。福島地裁平成3年4月9日決定(シノブ設計事件)なども、同様に建築の著作物性について厳しい判断を示しており、裁判所が一貫して慎重な姿勢をとっていることがうかがえます。 -
「通常加味される美的要素」を超えることの困難さ
裁判所は、原告建物のデザイン(切妻大屋根の片側葺き下ろし、勾配破風サッシ、インナーバルコニーなど)が、一定の美的創作性や設計者の試行錯誤の成果であることは認めつつも、それらは「一般住宅において通常加味される程度の美的要素」の範囲内であると評価しました。これは、現代の住宅デザインにおいて、様々なデザイン要素を組み合わせることは一般的であり、それ自体が直ちに「建築芸術」としての創作性を生むわけではないという厳しい見方を示しています。個々の要素が独創的であったとしても、その組み合わせの結果として、全体が「建築芸術」の域に達しているかどうかが問われるのです。 -
不正競争防止法による保護も限定的
商品形態の模倣として不正競争防止法による保護を求める場合、単に一部のデザイン要素が似ているだけでは足りず、商品全体の形態が実質的に同一であるといえるほどの酷似性が求められます。住宅のような複雑な形態を持つ商品の場合、この要件を満たすのは容易ではありません。 -
設計図や写真の著作権は別途考慮される
建物自体が「建築の著作物」と認められなくても、その建物を撮影した写真や、作成された設計図には、それぞれ独立した著作物性が認められる可能性があります。本件でも、写真は著作物として保護され、その複製行為に対して差止めや損害賠償が認められました。これは、建築プロジェクトに関わる様々な成果物が、それぞれ異なる法的評価を受けることを示しています。写真の著作物性に関しては、本判決が、撮影者の意図や工夫が凝らされた場合に創作性を認めるという従来の裁判例の傾向に沿ったものであると指摘されています。 -
意匠権など他の知的財産権の活用も重要
住宅デザインを法的に保護するためには、著作権だけでなく、意匠権の取得も非常に重要です。意匠権は、物品等の形状等や建築物の形状等、または画像の意匠を保護する権利です。特に、令和元年(2019年)の意匠法改正(令和2年4月1日施行)により、新たに「建築物」及び「内装」のデザインも意匠権の保護対象となりました。 これにより、本件判決当時にはなかった、建築物全体のデザインを意匠権で保護するという強力な選択肢が加わりました。もちろん、従来通り、特徴的な部材やユニットなどを「物品」として意匠登録することも依然として有効な手段です。住宅デザインを保護する上で、改正意匠法の活用は不可欠と言えるでしょう。 -
「ただ乗り」に対する一般不法行為の成否
控訴審で原告が追加した一般不法行為に基づく請求も退けられました。これは、著作権や不正競争防止法で保護されない行為について、直ちに一般不法行為が成立するわけではないことを示しています。公正な競争秩序を著しく害するような特段の事情がない限り、他者の成果を利用することも自由競争の範囲内と解される傾向にあります。
まとめ:住宅デザインと法的保護のこれから
積水ハウス事件は、住宅デザインの法的保護の難しさを浮き彫りにしました。特に、「建築の著作物」として著作権法による強力な保護を受けるためには、単なる「良いデザイン」や「売れるデザイン」を超え、「建築芸術」と評価されるレベルの独創性が不可欠です。この判断基準は、建築という実用性と芸術性が交差する分野における著作権保護のあり方について、深い洞察を与えてくれます。
しかし、これは住宅デザインが全く保護されないという意味ではありません。本件でも写真の著作権は認められましたし、設計図も著作物として保護される可能性が高いです。また、意匠権や商標権といった他の知的財産権による保護や、契約による保護も検討すべきでしょう。
住宅業界においては、他社のデザインを安易に模倣することは、紛争のリスクを高めるだけでなく、業界全体の創造性を損なうことにも繋がりかねません。一方で、過去のデザインから学び、それを発展させていくこともデザインの進歩には不可欠です。
この判例は、住宅デザインに関わるすべての人々にとって、自社の知的財産の適切な保護と、他者の権利への配慮という、二つの側面から法的リスクを再認識する良い機会となるでしょう。今後も、住宅デザインと法的保護をめぐる議論は続いていくと考えられます。